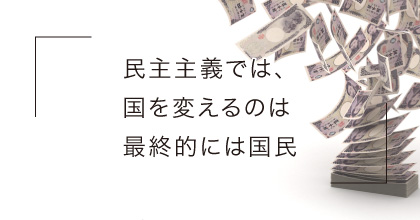
民主主義では、国を変えるのは最終的には国民
この連載の第3回で、財政再建に成功した国のモデルケースを紹介しましたが、これがわかっていても、できない国があります。日本もそのひとつです。理由は、前回、解説したように日本が民主主義の国で、政党は常に、支持者である有権者の方を向いているからです。
すると、財政支出の削減もできない、増税もできない。そこで、安倍政権は盛んに経済成長を打ち出します。2020年にPBの黒字化を主張していますが、それも財政支出の削減ではなく、経済成長による歳入のアップによって実現しようとしています。
しかし、経済成長率の見込みは甘くなるのが常で、PBの黒字化も難しいのが現実です。すると、さらに借金だけが増えていく悪循環が続くことになります。
この民主主義の仕組みがわかると、財政再建を可能にするのは、最終的には国民であることがわかります。借金が増え続けるまま先送りし、そのツケを将来に回して良いのでしょうか。しかも、その将来とは、遠い未来の話ではなく、いまの子育て世代の子どもたちの話なのです。
この子たちに重い負担を負わせないためには、社会保障費の削減や消費税の増税の痛みを、いまの私たちからともにも背負うことが必要です。有権者がその意識をもち、変わっていけば、政党の反応も変わるのです。
近年、赤ちゃんや子どもの投票権を親に付与するという議論が盛んになっています。民主主義では、投票権のない人の意見を吸い上げるのが非常に難しいからです。
では、この投票制度が実現したとき、子どもたちの投票権を託されたあなたは、いまの自分たちの既得権を守ってくれる政党に、これ幸いとすべて投票しますか。それとも、少なくとも子どもたちの投票権の分は、自分たちの既得権を削る政策を掲げている政党に投票しますか。
実は、この投票制度が実現しなくても、この選択が、いま、私たちに試されて投げかけられているように思います。
#1 日本政府の借金って、どういう状態なの?
#2 日本政府の借金はなぜこんなに膨らんだの?
#3 PBの黒字化って、借金が減るということ?
#4 財政再建が難しいのはなぜ?
#5 財政再建を実現する方法って、あるの?
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。




