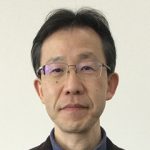パレスチナとイスラエルの問題や、いわゆる「カルト」の問題など、近年は戦争との関連や社会問題として、しばしば「宗教」が話題になります。日本人は無宗教であるとよく言われますが、本当にそうでしょうか。「宗教は自分には関係ない」という考えには再考の余地があるように思います。多くの人は広い意味での「宗教」に対する感覚をもっているのではないでしょうか。それを自覚することは、いろいろな意味で重要だと考えます。
『世界に一つだけの花』の「どれもみんなきれい」という言葉は宗教的
 「宗教」に対し、現代日本の多くの人は「自分とは関係のないもの」と考えているのではないでしょうか。とくに今から30年前に起こったオウム真理教の事件の頃から、「宗教」に対して距離を置こうとする人が増えてきたように感じます。しかし、そういう人たちに「宗教的な経験」がないわけではないと私は考えています。
「宗教」に対し、現代日本の多くの人は「自分とは関係のないもの」と考えているのではないでしょうか。とくに今から30年前に起こったオウム真理教の事件の頃から、「宗教」に対して距離を置こうとする人が増えてきたように感じます。しかし、そういう人たちに「宗教的な経験」がないわけではないと私は考えています。
たとえば、今は学校で習うらしいのですが、SMAPが歌った『世界に一つだけの花』(槇原敬之作詞作曲)という曲があります。この曲の歌詞は、とても宗教的だと私には思われます。この曲は、「花屋の店先に並んだ/いろんな花を見ていた/ひとそれぞれ好みはあるけど/どれもみんなきれいだね」と始まります。
通常、「きれい」という言葉は、「きれいでない」ものとの対比によって初めて「意味」をもちます。「長い」に置き換えるとわかりやすいと思います。1本の棒だけ見せられて長いかと問われても、答えられません。しかし「1mよりも長いか」、「隣の棒より長いか」と聞かれれば答えられます。これは、言葉の「意味」が相対的だということです。
ですから、たとえば、目の前にない他の花と比較して、「(目の前の花は)どれもみんなきれい」というのはわかるとしても、「どれもみんなきれいで、きれいでないものはどこにもない」というのは、通常の、相対的な意味を言い表わす言葉としては、おかしいわけです。こうした言葉が使われているのは、この歌が伝えようとしているものが、通常の「意味」を超えた「絶対的なもの」だからだと考えられます。さきほど、この歌が宗教的だと言ったのは、そういう理由からです。
この歌に共感をもつ人は今も多いようです。それは、多くの人が自分自身の中に「宗教的」と言えるものをもっているからではないかと思います。「宗教」とは何かということを正面から問題にすると難しいことになりますので、私たちが宗教的なものを経験していると思われる場面について、少しお話してみます。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。