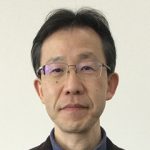生きることは「意味」に先立って絶対的に肯定されている
絶対的な「生」を経験するとき、私の人生は「生」の「現われ」であるという見方が生まれます。私の空腹について、それは「私のもの」ではなく、空腹の、今ここでの「現われ」である、と考えられるとすれば、それと同様に、私の人生も、「私のもの」ではなく、「生」の、今ここでの「現われ」であると考えられます。
このように自分を絶対的な「生」の「現われ」と見るというのは、自分を「生」に従属するものと考え、自分には主体性がないと考えるということとは違います。「生」が自分の外にあると考えられると、主体性がないということになるかもしれませんが、今の場合は、「生」は自分の「生」です。ですから、ここで考えられているのは、自分が主体性をもって生きることが、そのまま絶対的な「生」が生きることである、ということです。
このとき、それぞれの人の人生は、すべて、絶対的な「生」の「現われ」として絶対的に肯定されます。絶対的な「生」が「現われる」とは、「生」がある特定の状況に置かれることですから、それぞれの人の人生は、その状況にふさわしく生きるという課題をもっています。ただ、まず課題があって、それを果たすために人が生きるのではありません。課題は、人が生きる中で知られるものです。
さきに取り上げた「意味」という言葉を使うならば、意味が生きることに先立つのではなく、生きることが意味に先立つ、ということです。さきほどは、生きる意味を求めても、それを見出すことはできない、というお話をしましたが、それは、そこでは、生きることに先立って与えられている意味が求められていたからです。意味は生きることに先立って与えられているものではなく、一人ひとりが生きる中で探し求め、創り出してゆくものです。
このように、生きることはその意味に先立って絶対的に肯定されているということを、さきにお話した空腹の経験や、その他さまざまな経験を通して、多くの人は感じていると思われます。『世界に一つだけの花』の歌詞に多くの人が共感するのは、そのためだろうと私は考えています。
「どれもみんなきれい」というのは、すべての花の存在が、「絶対的なもの」によって、絶対的に肯定されているということであると理解できます。そうだとすると、この歌詞は広い意味で「宗教的」であり、また、「宗教的」な経験がないと共感できないものであると言えるのではないでしょうか。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。