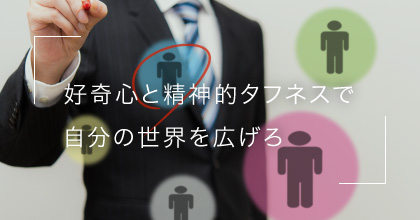学びを加速させるアドバイス学生時代の演劇が今に活かされている
教授陣によるリレーコラム/学びを加速させるアドバイス【15】
「学び」を深め、続けていくには、教室の外の経験や趣味が思わぬ力になることがあります。
私にとって、それは演劇でした。
私が高校生・大学生時代を過ごした1980年代は小劇場ブームでした。高校生の頃から、週末は大阪や京都の小劇場やホールに芝居を観に行っていました。大学に進学すると観るだけでは飽き足らずに、1年生の初めから学生劇団に入り、毎晩遅くまで芝居の練習や大道具製作に汗を流しました。
当時影響を受けたのは、つかこうへいさんでした。つかさんは1970年代にブームを巻き起こした劇作家・演出家であり、私より上の世代の演劇人でしたが、1980年代の演劇界でもその影響は大きかったように思います。劇団仲間の一人は後につかさんの演出助手となりました。
つかさんが書いた『熱海殺人事件』や『蒲田行進曲』といった戯曲には、今の時代では不謹慎と思われるような言葉や表現が多く出てきましたが、あえてそのような言葉や表現を用いることで、社会の片隅に追いやられた人々の辛さや、恵まれた立場にある人々の残酷さを浮き彫りにしていたと感じます。
私は学生劇団に入った当初、卒業後は演劇関係の職に就きたいと漠然と夢見ていましたが、やがてその夢は消えてしまいました。一言でいうと、周りの人がプロになるほどの実力者ばかりで、自分の実力のなさを痛感したのです。
今は毎クールのドラマで目にする実力派俳優となった同学年の仲間は、学生時代から観客を魅了する華がありました。ドラマのディレクターや映画監督となった仲間もそうでした。私は、努力ではどうしようもない彼らとの圧倒的な資質や能力の差を感じて、2年生の終わりに劇団を引退しました。
その後は法学部生らしく法律の勉強をしながら、演劇は観る側に回りました。研究者となった今でも、研究の合間に劇場に足を運んでいます。
法律学は座学が中心で、机の前で大量の文献を読み論文を執筆する日々です。そのなかにあって、生の人間が目の前で感情をぶつけあう演劇は、大いに研究生活の刺激になっています。
学生にも、そのような趣味を学生時代に見つけてほしいと思っています。私の場合は、演劇に親しんできたことで、現在、人前で講義する立場になってもさほど緊張しないし、教室でも声が通っています。演技の経験が生きているのだと思います。
このようなかけがえのない趣味は、ときに「学び」そのものと直結することもありますし、趣味を楽しむためにこそ勉強を頑張るというモチベーションにもつながります。
みなさんもぜひ、自分にとっての「学びを支える趣味」と出会いを大切にしてください。それはきっと、人生を豊かにする糧となるはずです。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。