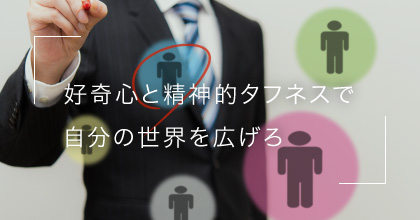学びを加速させるアドバイス急がば回れの学び術──あえて“分厚い教科書”を読む理由
教授陣によるリレーコラム/学びを加速させるアドバイス【6】
「学びを加速させるアドバイス」という言葉に矛盾するかもしれませんが、学生諸君には、あえて「急がば回れ」ということをお勧めしたいです。
確かに早いことには良い面があります。たとえば、司法試験に若く、早く合格すれば、経済的にも、実務に就く上でも大きなアドバンテージが得られるでしょう。また、勉強する上で生じる問題点について早く答えを得ることができれば、余った時間を有効に活用できるでしょう。
しかしながら、昔から「学問に王道なし」といわれるように、結果を出すのに時間をかけることは、無駄でないだけではなく、「学び」の質を高めるのにも大いに役立つといえます。
最短距離で正解にたどり着く場合、それを支える根拠も最低限のものだけということになることがあります。それに対して、様々な可能性を検討した結果として正解にたどり着く場合は、豊かな思考に基づく根拠に支えられることになり得ます。
ちなみに、法律の世界にも「教科書のトレンド」みたいなものがあり、やはり最近出版されて見栄えもよい本に人気が集まる傾向があるのですが、私は、どちらかといえば、昔ながらの本をしっかり読むということを重視しています。
いわば“古典”と呼ばれるような教科書は、ページ数も最近の本の倍ほどあり、なかなか気軽に手に取れるような代物ではありません。しかし、その教科書を読んで多くの先輩が法学を学び、議論を深めてきたのです。その意味では、要点を抑えて気軽に扱える最近の本よりも、実は学ぶことのできる内容に富んでいます。
現代という時代は、ありとあらゆるものを効率化し、スピードアップしていく流れにあります。
しかしながら、時間の許す限りという制約の範囲内ではありますが、効率一辺倒を追求するのではなく、とりとめもないことをあれこれと考えることこそが、本当の「学び」にとって重要ではないでしょうか。
答えに迷い、行ったり来たりしながら、自分の思考を鍛え、豊饒なものとしてほしいと思います。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。