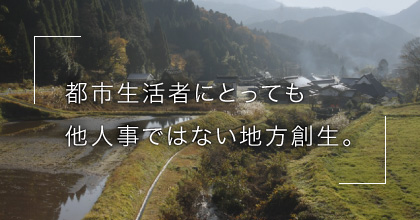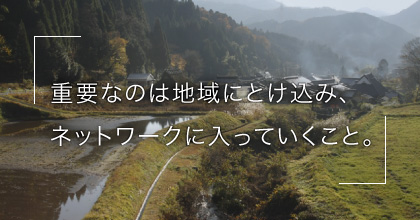学びを加速させるアドバイス学習意欲をそそるには、こまめに締切を課すことが大切
教授陣によるリレーコラム/学びを加速させるアドバイス【4】
自分が大学生だった頃は、将来自分が大学教員になるとは思ってもみませんでした。卒業後は農林水産省に行政官として入省。その6年目、イギリスの大学院に2年間留学させてもらったところ、そこでの勉強がすごく面白かったんです。実務を経験したうえで問題解決のために大学院で学ぶと役に立つことがわかり、将来的には大学で教えてみたいとも思うようになりました。その後、ローマの国連機関などで研究的な仕事に携わった経験を活かし、官僚としての実績をもとに論文を執筆し、霞が関で働きながら博士号を取得しました。8年間の海外赴任を含めた25年間、官僚として勤め、2013年より明治大学で教鞭を執っています。
大学教員の多くは、学生時代に学ぶ楽しさを覚え、自身が専攻する学問を教えることに喜びを感じているでしょう。しかし実務経験が長い私は、現実を理解する上で学問が役に立つことを学生に伝えるように心がけています。そういった考えから、私の講義を聴けば今日のニュースを理解することや就職活動に役立つとアピールし、また講義内容も、例えばトランプ関税が話題になればそれを素材に経済学のツールを説明するといったように、社会とのつながりを実感できるように工夫しています。
たとえば、新聞記事を読ませ、それをもとに授業を展開するのも工夫の一つです。学生からすると、自分に直接関係のない抽象的な話をされてもピンとこない。現実の社会や、就活など学生自身の近い将来の利益とつなげて伝えることが大切です。また、授業の最後に毎回小テストを行うようにもしています。人間は遠い締切は先延ばしにする傾向があり、期末テストだけでは、その直前に勉強すればいいと思ってしまうからです。小テストという締切を授業時間内に毎回課すことで、学生をやる気にさせるよう努めています。
これらは教職に限らず、部下や後輩の教育にも重要な視点ではないかと思います。誰もが自主的に学んでくれるわけではありません。「自分にとって、どう役に立つのか」という部分を示してあげることが大切なのではないでしょうか。
一方、自身が時事問題・社会問題を学びたいと考えたときにも、新聞記事はいい取っかかりになるでしょう。たとえば総理の発言内容など、新聞であれば事実関係も確認されていますし、もとの趣旨を損なわないよう、非常に注意深く要約されています。たとえば米の輸入制度は複雑ですが、私が取材で話した内容を、記者が自分で理解したうえで整理して記事にしてくれるので、とてもわかりやすく、効率よく情報を得ることができます。最近は誰でもSNSで発信できるため、ネット上の情報は嘘が多く玉石混淆です。裏付けのあるものを積極的に情報源として使うのも、学びを加速させるうえで大切だと思います。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。