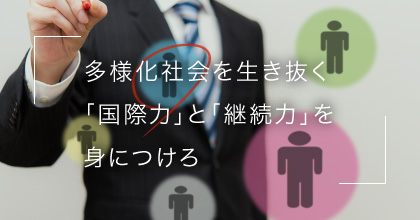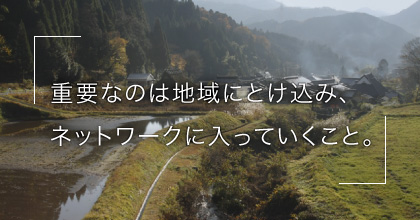
重要なのは地域にとけ込み、ネットワークに入っていくこと。
いま、田園回帰志向が強まっていると言われます。内閣府の世論調査(2014年)でも、「将来農山漁村に定住したい」20代男性は47.4%で、約10年前の同じ調査の34.6%より高くなっています。30代女性は31.0%、40代女性は31.2%と、女性のこの世代は、前回調査から倍近く増えています。その理由の特徴は、農山漁村の方が子育てに適していると思われていることです。この世代が夢や憧れではなく、現実的に田園回帰を捉えているのがわかります。
もっとも、この調査は願望を聞いているので、実際に移住するとなると、様々な問題があり、実現するのは大変です。最も切実な問題は、仕事でしょう。例えば、地方で農業に従事しようと思っても、農業技術も、土地も、資金もない都市生活者にとっては、いきなり実践することは、困難です。では、どうすれば良いのか。すぐに農業専業を目指すのではなく、「半農半X」から始めることです。実際、“プロ”の農家でも、多くは兼業農家です。つまり、「半農半勤め人」であっても、まったく構わないのです。週末だけ、農山村で暮らすウィークエンドファーマーから始めても良いでしょう。あるいは、移住しても「半X」の部分に都市生活での経験を活かせる場合もあります。例えば、インターネットなど情報通信環境の発達を利用して、「半農半翻訳家」とか、「半農半ウエブデザイナー」をしている人も実際にいます。また、地域の資源を活かした6次産業に関わる人もいます。農山村には、作物やもの作りはプロでも、マーケティングや営業、販売は得意ではない人も多くいます。その部分に、都市生活の経験を活かすこともできるでしょう。
農業は、最初は趣味程度でも構いません。収穫物が余るようになったら、直売所に持って行くとか、自分の車で移動販売をしても良いかもしれません。重要なのは、そうやって地域のコミュニティにとけ込み、ネットワークに入っていくことです。すると、周りの人たちのサポートが得られるようになり、生活のハードルは低くなってきます。仕事はもちろん、地方での生活を楽しく、豊かにするためには、ネットワークに入ることが最も大切です。成功のポイントは、急がば回れ、なのです。
次回は、地方への段階的な関わり方について紹介します。
#1 「地方創生」って、都市には関係ないでしょう?
#2 田園回帰って、どうやったら上手くいく?
#3 地方の生活に関わってみたい!! でも、どうやって?
#4 地方での活動を成功させる方法は?
#5 都市か地方の二者択一じゃなくても良い?
#6 農学部が人気なのはなぜ?
#7 でも、地方は消滅するって本当?
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。