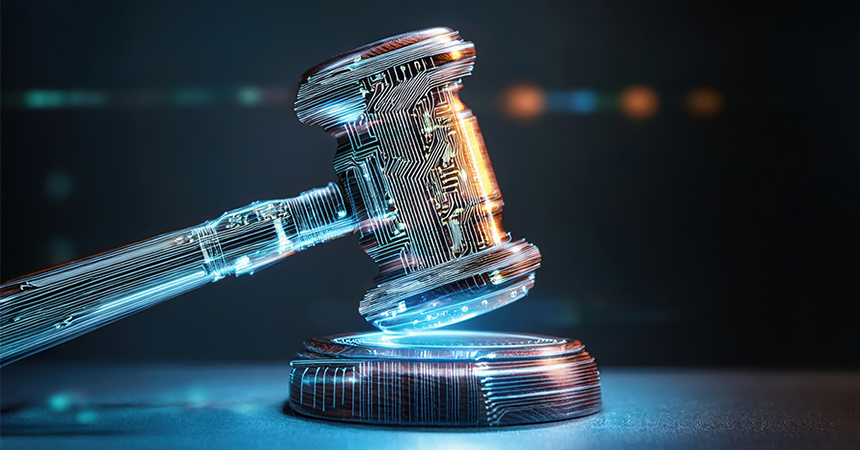
スマートフォンひとつで買い物も銀行手続もできる時代。では、裁判はどうでしょうか? 日本では2023年以降、民事訴訟手続の一部がオンライン化されました。一方で、情報の質や当事者の「満足感」、そしてデジタル格差といった課題も浮上しています。制度を使うのは誰か、そして誰のための改革なのか──司法のデジタル化の最前線を追います。
裁判もついにオンライン時代へ
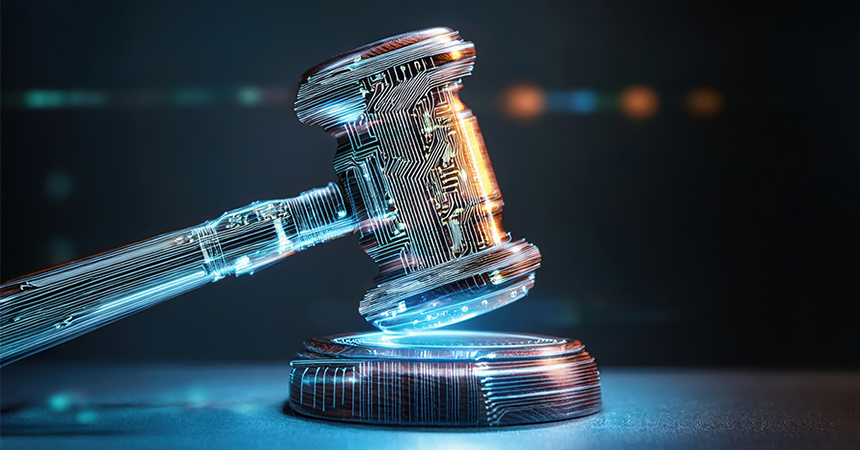 民事訴訟制度や民事執行制度、倒産処理制度などの司法制度は、国家が国民に提供する司法サービスの一環として整備されているものです。これらには国家統治のための仕組みという側面もありますが、それ以上に国民の権利を守るための重要なツールであるため、なによりも国民が利用しやすい制度であることが求められます。
民事訴訟制度や民事執行制度、倒産処理制度などの司法制度は、国家が国民に提供する司法サービスの一環として整備されているものです。これらには国家統治のための仕組みという側面もありますが、それ以上に国民の権利を守るための重要なツールであるため、なによりも国民が利用しやすい制度であることが求められます。
すなわち、裁判制度が存在しなければ、社会は弱肉強食の世界になりかねませんが、国家はそのような状況を防ぐために、裁判制度を整備しているのです。しかし、手続が複雑すぎたり、無駄な時間がかかるなどして利用しづらい制度では意味がありません。そのため、法律の改正や解釈の変更を通じて、利用者が利用しやすいように制度の改善が行われてきました。
そのひとつが、司法のデジタル化の議論です。日本における民事裁判手続のデジタル化は、2001年の司法制度改革審議会の意見書で訴訟手続へのIT導入が提言され、2004年の民事訴訟法改正でオンラインによる裁判所への申立ての制度を認める定めが置かれました。
しかし、法律の世界には保守的な傾向があり、デジタル化には抵抗があったため、なかなか本格的な整備は進みませんでした。世界に遅れをとりながら、政府全体としてデジタル化に向けた動きを本格化させたのは2010年代の後半になってからでした。
2018年には内閣官房が「裁判IT化に向けた取りまとめ‐『三つのe』」という報告書をまとめ、日本における改革の方向性を定めました。これはe提出(主張・証拠のオンライン提出等)、e事件管理(訴訟記録へのオンラインアクセス等)、e法廷(ウェブ会議の導入・拡大等)の3つを柱とするものでした。
さらに、コロナウイルスのパンデミックの影響で、2019年からはウェブ会議システムを利用した訴訟の準備手続が裁判所で例外的に認められるようになりました。そして、2020年からは法制審議会で具体的な法改正に向けた作業が始まり、2022年には国会で民事訴訟法が改正されました。この手続デジタル化のための法整備は、人事訴訟、家事事件、民事執行、倒産処理など、その他の民事裁判手続の分野にも及んでいます。
こうして民事裁判手続をデジタル化するための根拠となる法制度が整備され、これからは現実にそれを実装・完成するというプロセスに入っていくことになります。
そもそも裁判手続のデジタル化とは、具体的には文書を電子化してインターネットを通じて裁判所へ提出することができるようになったり、裁判所に実際に出頭しなくてもウェブ会議等を利用して参加することができる手続の種類を拡大させることを指しています。
実際、裁判所におけるデジタル機器の整備やオンラインシステムの導入については、全国の地方裁判所およびその支部で進展しており、2024年3月からは民事訴訟でのオンラインによる口頭弁論も可能となりました。
ただし、ウェブ上での証拠調べや事件記録・管理のデジタル化など、改正法の全面的な施行にはまだ至っていない点もあり、今後の課題となっています。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。




