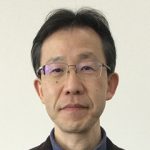「生」は何か他のもののためにあるのではない
通常、私たちは生きることに意味を求めますが、果たしてそれは「生」に対する正しい態度であるのか、という反省がそこで生じます。「生」に意味を求めるとは、「生」を「生」以外のものによって根拠づけようとするということです。しかし、「生」を「生」以外のものによって根拠づけることはできるのか。それが問題です。
さきほどは、自分の人生を他者のための手段と考えることはできないと言いましたが、ここで問題になっているのは、誰の人生であろうとも、そもそも生きるということに対して意味を考えること自身が、生きることをその意味の手段としてしまうことになるのではないか、そして、それは生きるということに対する態度として正しくないのではないのか、ということです。
たとえば「愛」に対してその意味や目的を問うのはふさわしいことではない、ということには多くの人が気づいていると思います。恋人に「あなたは何のために私を愛しているのですか」、「私を愛することにどんな意味があると思っているのですか」と聞かれたら、困ってしまいます。「生」についても、同じことが言えます。
何か他のもののために存在しているのではない、それ自身のために存在しているというところに「生」の本質があると考えられます。「生」の存在は、意味があるから肯定されるようなものではなく、「絶対的に」自己自身を肯定するものである、ということです。
このことに気づくことは、自分の中に「絶対的なもの」を見出すということです。これは「宗教的」という言葉がふさわしいような、大きな経験です。「絶対的なもの」をはっきり経験するのは、一部の宗教家だけかもしれませんが、ふだんの生活の中で、私たちが「絶対的なもの」を感じるということはあるように思います。
たとえば、おなかがすいたときのことを考えてみてください。おなかがすいたと感じ、ものを食べるのは私ですが、空腹そのものは私を出発点とするものではなく、もっと大きなものから来ています。そのことに気づくとき、私たちは、自分の中に自分を超えた大きな命を感じます。このようにして感じられる大きな命は、今、絶対的な「生」と呼んだものにほかならないと私は考えています。
「絶対的なもの」を経験すると、私たちは自分を「絶対的なもの」から見るようになります。今の場合だと、「生」が絶対的であることを経験して、私たちは、「私」を出発点として「生」を知ることはできない、むしろ、「生」を出発点として「私」とは何かを知るべきではないか、と考えるようになります。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。