
圧縮技術の進展が生んだハイビジョン
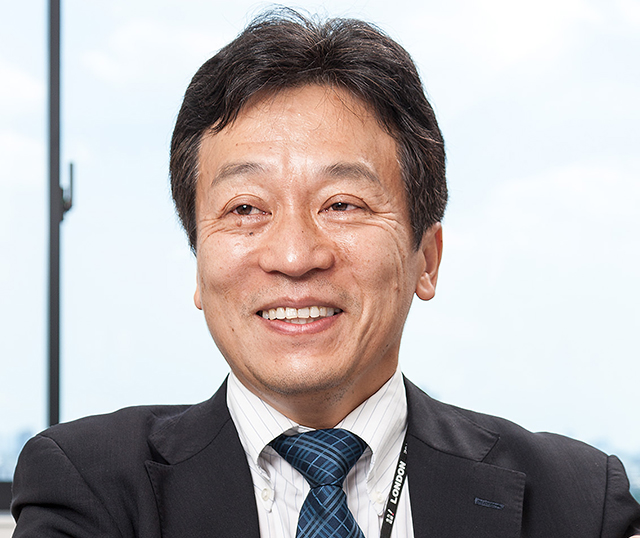 約90年前の1926年、“テレビの父”といわれる高柳健次郎によって、「イ」の字を伝送・表示したことに端を発し、遠くの事象をリアルタイムで放映することの追求が始まった。テレビの歴史の幕開けである。その後、1953年に日本でテレビ放送が始まり、1960年にはカラーテレビの本放送も開始された。早くもその4年後に、NHKはハイビジョンの開発に着手している。私は大学卒業後、NHKに入局、地方局勤務を経て、1986年にNHK技術放送研究所に配属されたが、その時期NHKはハイビジョンの伝送実験を開始、私もその研究開発に携わることとなった。
約90年前の1926年、“テレビの父”といわれる高柳健次郎によって、「イ」の字を伝送・表示したことに端を発し、遠くの事象をリアルタイムで放映することの追求が始まった。テレビの歴史の幕開けである。その後、1953年に日本でテレビ放送が始まり、1960年にはカラーテレビの本放送も開始された。早くもその4年後に、NHKはハイビジョンの開発に着手している。私は大学卒業後、NHKに入局、地方局勤務を経て、1986年にNHK技術放送研究所に配属されたが、その時期NHKはハイビジョンの伝送実験を開始、私もその研究開発に携わることとなった。
ハイビジョンは周知のように高精細な画像を実現するもので、2000年のBSデジタル放送、2003年の地上デジタルテレビ放送開始以降、ハイビジョンテレビは広く一般に普及浸透した。かつて、デジタルハイビジョンは21世紀の先になると予測されていた技術だった。アナログに比べてデジタルは情報量が圧倒的に多い上、ハイビジョンは標準テレビの5倍の情報量を持つが、情報の圧縮技術の確立には相当の時間がかかるとみられていた。さらに放送には帯域という絶対的な縛りがあり、既存の帯域内で大容量の情報伝送を実現することの難しさが指摘されていたのである。だが’90年代に入り、ISOにより設置された動画専門家集団であるMPEGが、映像データ圧縮の標準化活動を進めたことで技術が進展、デジタルハイビジョン放送が現実のものとなっていった。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。




