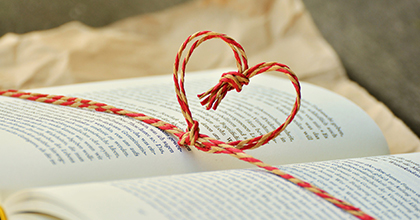「経済安全保障」という言葉がトレンドになっています。日本では2022年5月に経済安全保障推進法が成立し、政府は半導体などのサプライチェーンを国内で強化して、基幹インフラを外国の脅威から守るとしています。他方、米国では、2019年の日韓の輸出規制をめぐる対立を経済安全保障の文脈で解釈する議論が盛んになっています。
経済安全保障とエコノミック・ステイトクラフト
 国際政治経済の分野において、外交・軍事・安全保障は「ハイ・ポリティクス」、経済は「ロー・ポリティクス」との位置づけで区別されていましたが、近年、両者を融合した「経済安全保障」が注目を浴びています。ただし、「経済安全保障」という日本語には明確な唯一の定義があるわけではなく、英語の「economic security」を直訳したものになります。
国際政治経済の分野において、外交・軍事・安全保障は「ハイ・ポリティクス」、経済は「ロー・ポリティクス」との位置づけで区別されていましたが、近年、両者を融合した「経済安全保障」が注目を浴びています。ただし、「経済安全保障」という日本語には明確な唯一の定義があるわけではなく、英語の「economic security」を直訳したものになります。
私は現在、ハーバード大学にて在外研究を行っていますが、どこに行ってもeconomic security(経済安全保障)の話で盛り上がり、経済安全保障のセミナーはハーバードのみならず、アメリカの学会でも最もホットなトピックになっています。
米国では、経済安全保障に関連して「economic statecraft」がキーワードになっており、こちらのほうが専門用語としてより多く使われている印象です。日本語での直訳は難しく、論文でもしばしば「エコノミック・ステイトクラフト」として表記されます。意味合いとしては「経済的な手段を用いて地政学的な国益を追求する」といったところです。
いずれにせよ、経済政策によって地域の安全や国益などを守るというのがeconomic securityとeconomic statecraftの中心的アイディアであり、そのどちらが包括的な概念であるかについては議論があります。
私の専門のひとつは、日本と韓国の経済安全保障における比較分析ですが、同じ通商国家であり経済大国である日韓を比べてみますと、両国内で経済安全保障の考えが盛んになった経緯には興味深い違いが見られます。
まず、日本の場合は、コロナ禍でのグローバル・サプライチェーンの崩壊が念頭にありました。たとえば中国に生産拠点を置く国内企業がコロナの影響で製品を生産できなくなると、これは日本経済の観点からも非常に大きな打撃となります。
このグローバル・サプライチェーンのレジリエンス(弾力性)をいかに活性化させるかという課題のもと、日本政府は経済安全保障の関連法を整備するなどの政策をおこなってきました。
一方の韓国の場合は、コロナ禍以前に、旧日本統治下での徴用工をめぐる問題で日本政府と政治的な対立が生じ、それが経済や安全保障の分野での対立へとエスカレートしたことが背景にあります。
詳しくは後述しますが、この対立の間の日本政府の対韓政策について、韓国内では「日本が経済的な手段を使って韓国の国益を脅かした」といった見方がなされ、それによって経済安全保障の議論が活発化したという経緯があるのです。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。