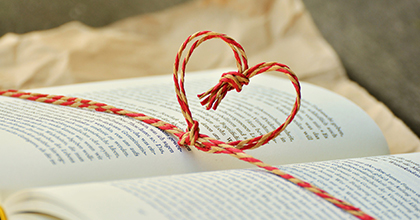経済的関係を利用した「相互依存の武器化」とは何か
経済安全保障を理解するためには、国際関係論における「経済的相互依存(economic interdependence)」を把握しておく必要があります。米国の国際政治学者が1970年代に提唱した「相互依存論」に由来し、簡単に説明すれば、国家間が(経済的に)交流し互いに依存する関係が深まれば、究極的には民主主義とリベラルな市場経済による世界平和が構築されるという主張です。
日韓を例にすると、半導体をめぐる相互依存が挙げられます。1990 年代に日本の半導体産業が急速に競争力を失い、韓国が追い上げていく過程において、国内需要が急減した国内半導体素材・製造装置企業は代替的な供給先を必要としました。結果、韓国の半導体産業は日本からの供給に頼り、逆に日本の半導体素材・装置産業は韓国の需要に頼る関係が生まれました。
このようにして形成される経済的相互依存は、関係国に共通の利益を与え、それを縮減する場合のコストやリスクを高めるがゆえに、政治的には両国に協調を促す作用が働くと考えられてきました。
しかし、近年の経済安全保障においては、この経済的相互依存を逆手にとった「相互依存の武器化(weaponized interdependence)」という概念が注目されています。
実際、韓国内でこの問題が表面化したのが、2019年の日本による韓国への輸出規制でした。日本から半導体の素材が輸入できなくなり、国内外に売却する半導体の生産が窮地に追いやられてしまったのです。
ことの発端は2018年10月、韓国の大法院(日本の最高裁に相当)が日本統治下の朝鮮半島で日本企業が動員したいわゆる徴用工に関し、企業に強制労働の被害についての慰謝料を命じた判決に遡ります。日本政府は国家および個人の請求権問題は日韓請求権協定(1965年)によって解決したとする立場をとっているため、判決に対して強い懸念を示しました。
そんななか2019 年 7月、日本政府は韓国に対して半導体素材 3品目(フッ化ポリイミド、レジスト、フッ化水素)の輸出管理を強化しました。輸出について優遇する「ホワイト国」から韓国を除外し、事実上の輸出規制に踏み切ったのです。
韓国国内でこの動きは「徴用工問題の報復」と受け取られ、対日感情は悪化し、日本製品の不買運動が拡大しました。当時の文在寅政権は同様に日本を「ホワイト国」から外し、日本の措置をWTOに提訴しました。実質的な経済制裁に対して、同等の対応を講じたということです。
当時、米紙ウォール・ストリートジャーナルが「日本は貿易を武器化した」という論陣を張って大きな議論になりましたが、この一連の応酬こそ、まさに経済的相互依存を利用した「相互依存の武器化」であると言えます。
日本側の言い分は「輸出規制の理由は韓国の安全保障上の懸念にある」というものでしたが、韓国側は完全に「歴史問題の報復としての経済を武器化した」と考えました。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。