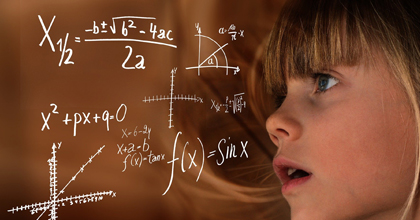
>>英語版はこちら(English) 高校の新学習指導要領が2022年度から導入されます。今回の改訂のポイントの一つは、「思考力、判断力、表現力」の育成を重視することです。それに伴って各教科において教え方改革が始まりますが、数学における一つの考え方として、コンピュータを用いた学習が欠かせなくなると言います。それは、どのような学習法なのでしょう。
社会問題を数学的に捉え、考える能力を養う
 「思考力、判断力、表現力」は、現代社会を生き抜き、活躍するために必須の能力であると言えます。これらを重視する新しい学習指導要領が導入されることにより、授業での教え方や評価の仕方にも改革が求められてくると思います。
「思考力、判断力、表現力」は、現代社会を生き抜き、活躍するために必須の能力であると言えます。これらを重視する新しい学習指導要領が導入されることにより、授業での教え方や評価の仕方にも改革が求められてくると思います。
私は数学が専門なので、ここでは数学の話をしますが、数学において従来は、知識や技能を養う学習が中心で、計算の仕方や問題の解き方を習得することに重点がおかれていました。
それに対して、思考力、判断力、表現力を重視するという方針により、「計算による問題解決をすること」に加えて、「事象を定式化すること」、「問題解決の構想を立てること」、「計算結果を事象にフィードバックすること」が求められていきます。すなわち、若い人には、社会問題や自然現象を数学的に捉え、数学を通して考えたのちに再び社会問題や自然現象へフィードバックできることが期待されるようになります。
例えば、ミクロ経済学では需要曲線といって、ものが売れやすい価格設定の捉え方があります。ここには従来から数学が用いられているわけですが、高等学校の数学はこのような実用を前提とした数学をほとんど取り扱ってきませんでした。
あるいは、最近の卑近な例で言えば、新型コロナウイルスの蔓延によって、飛沫を飛ばさないことに関心が高まっていますが、くしゃみによって飛沫がどれくらい飛び、散らばるのかを、日常の経験からなんとなく捉えるのではなく、スーパーコンピュータを使ってシミュレーションを行うことで、数学を通してフィジカル・ディスタンシングの目安を考えたりすることができます。
つまり、目の前で起きている事象を経験則や感覚的に捉え判断するだけではなく、そこに法則性を見出し、その法則を表す式を考え、その式の計算結果によって問題解決の想定を立て、事象にフィードバックできるような人材の育成が望まれるようになります。
そのためのキーワードとして「思考力、判断力、表現力を養う」ことがとても重要になるのです。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。




