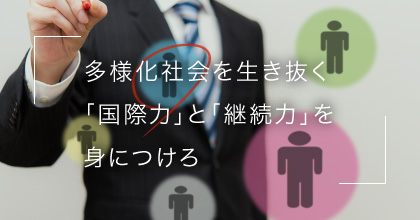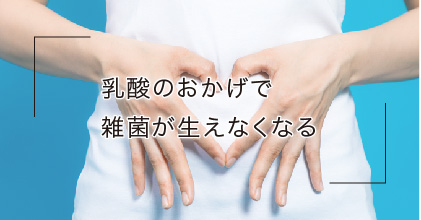
乳酸のおかげで雑菌が生えなくなる
多くの発酵食品ができる過程で乳酸菌が働いていますが、もともとは自然界にいる乳酸菌が、それとわからずに使われていました。味噌や醤油も、原料の米・麦・豆などの穀物および蔵や樽に付いている乳酸菌が利用されていたのです。乳酸菌が生育して乳酸を出すと、麹菌や乳酸菌と同様に「発酵食品」に欠かせない「酵母」がうまく育つようになります。乳酸菌と酵母が出す香り成分によって、発酵食品は香りや風味が良くなり、またタンパクや核酸の分解の結果、旨味が生じます。さらに、乳酸菌の働きの重要なポイントは「抗菌作用が強い乳酸」を出すことです。「にゅうさん」というとちょっとやさしげに聞こえますが、乳酸は有機酸という弱酸で、当然その環境を酸性化します。そして食中毒菌や腐敗菌などを殺す力(抗菌力)がとても強いのです。乳酸発酵の結果、食品が腐らなくなり、できあがった発酵食品は保存性が高く、さらに栄養価も高くなり、風味や旨味が増すのです。
古代の人は、それを経験則で知っていて乳酸菌を利用したのでしょう。もちろん、乳酸菌の発酵が続けば酸化が進み、食品が酸っぱくなってしまいます。例えば、ぬか味噌にも乳酸菌が生きていますが、漬け過ぎると漬物が酸っぱくて食べられなくなります。良いタイミングで食材を取り出したり、食品によっては殺菌することも必要です。ワインづくりでは、マロラクティック発酵といって、赤ワインを美味しくするために乳酸菌が使われますが、出来上がったワインの保存中に乳酸菌が生きていると酸っぱくなって美味しくなくなってしまいます。そこでパスツールによってパスチャライゼーションという低温殺菌方法が開発され、時間が経っても美味しく飲めるようになりました。日本酒にも「火入れ」という加熱殺菌の過程があり、乳酸菌を殺菌します。ビールに乳酸菌が生えるとビールの味が台無しになってしまうので、酸敗防止の為に乳酸菌を生えなくするホップを入れたのが現在のビールの始まりです。
このように、乳酸菌を上手く生かしたり殺したりしながら、人類は発酵食品を発達させてきたのです。そのなかで、生きたままの乳酸菌を大量に食べる食品がヨーグルトなのです。
次回は、牛乳がヨーグルトになる仕組みについて解説します。
#1 乳酸菌は伝統的な発酵食品の「影の主役」
#2 乳酸菌を使うと美味しくなるのは、なぜ?
#3 牛乳はどうやってヨーグルトになるの?
#4 胃酸でも死なないピロリ菌を乳酸菌が殺す?
#5 乳酸菌は人の免疫力を高める?
#6 ヨーグルトは薬になる?
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。