
芥川龍之介といえば、日本を代表する作家のひとりです。「羅生門」や「鼻」、「蜘蛛の糸」など、数多くの名作を残し、100年以上経った現代でも読み継がれています。一方で、この100年間の研究の中で、はじめて見えてきた芥川龍之介の実像もあると言います。
芥川龍之介以前からあった技巧をめぐる議論
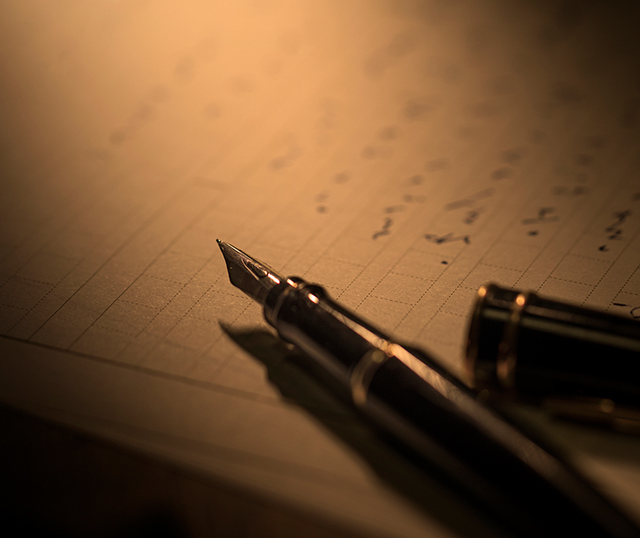 芥川龍之介は「新技巧派」と呼ばれ、文学史の教科書や国語便覧などにも「新技巧派」といえば芥川龍之介、ということが書かれています。あたかも、芥川龍之介の登場によって、彼の技巧的な作品が注目され、「新技巧派」というイメージが形作られたかのように思われます。
芥川龍之介は「新技巧派」と呼ばれ、文学史の教科書や国語便覧などにも「新技巧派」といえば芥川龍之介、ということが書かれています。あたかも、芥川龍之介の登場によって、彼の技巧的な作品が注目され、「新技巧派」というイメージが形作られたかのように思われます。
ところが、実は、大正時代の文壇では、彼の登場以前から、「技巧」は喧々囂々の議論のキーワードだったのです。
それが、なぜ、芥川龍之介の代名詞のようになったのかを研究していくと、彼と彼の周囲の仲間たちの人間臭さや、芥川龍之介という作家の深み、凄みがあらためて感じられるのです。
そもそも、小説とは、明治時代に西洋から輸入された概念です。そうして始まった近代文学の流れの中で、フランスに興った自然主義文学が日本でも勃興します。
そこで重視されたのは、あるがままの現実や自分を描く、ということです。その考えの下では、技巧とはわざとらしい、ずるいもの、あるいは「こしらえもの」として否定的に捉えられました。
ところが、そのあと反自然主義の動きが起こってきます。文学にとって技巧は大事ではないか、技巧を見直そうという議論が起こったのです。その議論は大正時代へと続いていきます。
一方、芥川龍之介は、大正4年に彼の代表作のひとつになる「羅生門」を発表します。しかし、当時はほとんど話題になりませんでした。
芥川龍之介が注目されるきっかけになったのは、翌大正5年に発表した「鼻」が、彼の師匠である夏目漱石に絶賛されたことです。
それでも、夏目漱石の弟子たちや、芥川龍之介も立ち上げに加わった「新思潮」という同人誌に参加する仲間内で、漱石先生が芥川を褒めたらしい、と話題になったくらいで、文壇内では、まだまだ、駆け出しの新人のような見なされ方だったと言えます。
ところが、大正6年に「時事新報」に掲載された「羅生門の後に」という文章の中で、芥川龍之介は、「自分がしばしば新技巧派と呼ばれるのは迷惑である」ということを書きます。
確かに、大正6年は新技巧派に関する議論が盛り上がった時期でしたが、この時期に、まだ新人扱いの芥川龍之介を、新技巧派と注目するメディアはほとんどありません。
ところが、これ以後に、芥川龍之介のこの発言が取り上げられ、彼の作品の技巧性などが論評される機会が増えていくのです。
しかも、当初は、芥川龍之介自身が言ったように、彼は新技巧派とは言えないという論調だったものが、たびたび新技巧派という観点から論じられるために、むしろ、芥川龍之介に新技巧派というイメージが定着していくことになるのです。
つまり、「羅生門の後に」という文章は、芥川龍之介によるセルフプロデュース戦略の始まりであり、メディアや世間の読者は、それに、はまっていったと見ることができるのです。
では、芥川龍之介は、なぜ、そのような戦略を仕掛け、それに成功したのでしょうか。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。




