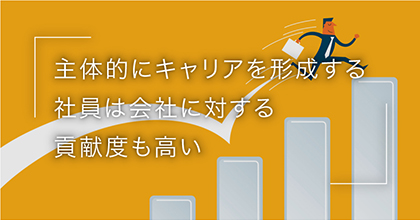
主体的にキャリアを形成する社員は会社に対する貢献度も高い
経団連が会員企業に対して行った人材育成に関する調査では、社員のキャリア形成の現状では7割の企業が会社主導で行っていると回答していますが、一方、今後については、約6割の企業が社員の自律性を重視すると回答しています。
これを見ると、現在は過渡期であることがわかります。その背景には様々な要因があると思いますが、大きいのは、社員すべての人材育成を会社主導で一律に行う伝統的なやり方では、社会の変化や多様化についていくことが難しいということです。
たとえば、2020年3月頃から日本でも大流行したコロナ禍によって、社会や企業を取り巻く環境は急激に変化しました。このとき、従来の価値観や体験にとらわれていると、変化に対応できず取り残されかねません。そこで有効なのは、人材の多様性です。
そもそも人は多様です。同じ会社で働く人たちも、本来は多様な経験や考え方をもっています。それを一律に、ひとつの企業文化に統一していっては、団結や協調には有効でも、社会の変化や多様化に対応することが難しくなります。
むしろ、人材の多様化を進めることが、企業が生き残り、成長していくには有効です。私たちは、いま、そういう時代に生きているのです。
では、社員のキャリア自律をどのように進めていくのか、それは企業もまだ模索していることが、経団連の調査の数字に表れていると思います。
たとえば、社内公募制など社員が自身の希望をキャリア形成に活かせるような制度を整えている企業も増えています。また最近では、社員に副業やボランティア活動を認める会社が出てきています。一見、本業とは関係のない活動ですが、そこで得られた経験や新たな人との繋がりが、本業に活きるという考え方です。
つまり、社外の活動をすることによって、本業に対して新たな見方や意味づけが見出され、それが創意工夫や新たなパフォーマンスに繋がっていくのだと考えられています。
社員からすれば、それは本業に対する新たな経験値、すなわち新たなキャリアの形成に繋がっていきます。
しかし、社員の主体的なキャリア形成を会社がどう支援するか、またどこまで認めるかについては、企業によって考え方も様々です。
たとえば、社員が主体的にキャリア形成をするという場合、せっかく育成した人材が他社でも活かすことができるスキルや知識を身につけ転職してしまうのでは、と考える経営者もいるかもしれません。また、副業やボランティアを認めるにしても、本業に支障がでるようでは意味がありません。そこでこれまでは、社員の主体的なキャリア形成などにはあまり乗り気ではない企業も見られました。
でも、実は主体的にキャリア形成を行う社員がみな転職をするのかというと、そんなことはありません。むしろ、自律的にキャリア形成を行っている社員は組織コミットメントも高い、という研究結果もあります。つまり、自律的にキャリア形成を行っている社員は、会社への貢献度も高いと言えそうです。
企業の今後の課題は、自律的なキャリア形成と会社主導の教育とのバランスです。それによって、将来的に自社を支えていく有能な人材を育てる新たな仕組みを見出すことができると思います。
次回は、個人が模索する主体的なキャリア形成について解説します。
#1 主体的なキャリア形成とは?
#2 主体的なキャリア形成は企業にとって有効?
#3 主体的なキャリア形成のためにはなにをすれば良いの?
#4 主体的キャリア形成で幸せになれるの?
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。




