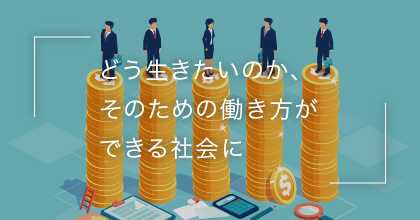
どう生きたいのか、そのための働き方ができる社会に
国際基準になっている「同一価値労働同一賃金」には、人々の多様性を認めながら、賃金の公平性を実現するという考え方があります。それは、一人の人にとっても、多様な生き方に対応した働き方が可能になるということでもあります。
例えば、近年、関心が高まっているリカレント教育(本来の意味は、フルタイム就業とフルタイム就学を交互に行うこと)のスタイルで、社会人になっても定期的に学校などで学び、新しい技能やスキルを身につけて、ワンランク上の職務に就くという働き方も可能です。
また、行きたいときに留学して、また再就職するということもできるでしょう。実際、欧米などではそうしたライフスタイルの人も多くいます。
さらに、女性は妊娠、出産、子育てのために退職を余儀なくされることがあります。数年後に再就職しようとしても、良い職はなかなか見つかりません。
でも、非正規雇用であってもそれなりの収入が得られたり、あるいは、子育ての合間に教育を受けて、以前よりも良い職務に就くことも可能であれば、女性の働くモチベーションは高まるのではないでしょうか。
要は、「パートタイム・有期雇用労働法」が国際標準の賃金制度に近づく一歩となるのであれば、企業経営者は新たな発想をもつように変わらなければいけませんが、働く側も、新たな発想をもって自分の生き方を考えることが求められると思います。
実は、最近の学生でも、専業主婦志向が少なからずあります。専業主婦がいけないとは言いませんが、それが自分の生き方なのか、自分らしさなのか、は考えることが必要です。
男は一家を支えなければいけないという「常識」も、女は働く男を支えなければいけないという「常識」も、若いうちは給料が安くても我慢しなければいけないという「常識」も、転職はリスクで定年までひとつの会社に勤め続ける方が安心という「常識」も、これからの日本社会では通用しなくなっていくでしょう。
そのとき、問われるのは、ひとりひとりの生き方だと思います。どう生きたいのか、そのための働き方ができる社会に、日本も向かおうとしていると思います。
#1 非正規雇用労働者に対する格差がなくなる?
#2 同一労働同一賃金が実現する?
#3 日本の賃金制度は普通じゃない?
#4 公平な賃金制度は企業にとってマイナス?
#5 生き方に合わせた働き方ができる?
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。



