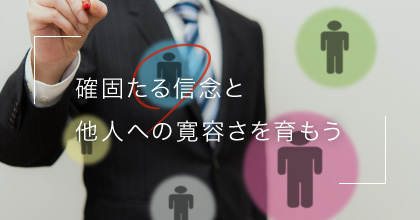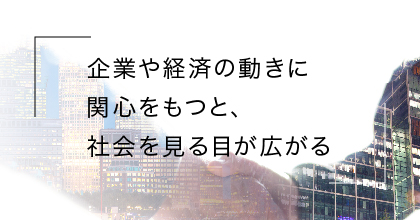
企業や経済の動きに関心をもつと、社会を見る目が広がる
この連載の最初に、日本では敵対的TOBはわずかと述べましたが、乗っ取り的なTOBもあったことはあります。
例えば、あるアパレル会社が、あるファンドに目をつけられ、株式買い付けを行われたことがあります。
そのアパレル会社は堅調な経営でしたが、それにしては株価が安く、しかも内部留保が非常に大きいことが目をつけられたきっかけでした。つまり、ファンド側は、少ない資金で大きな資産を得られるチャンスだったのです。
結局、この株式買い付けは失敗に終わりましたが、上場企業であって、大きな内部留保があるにもかかわらず、株主たちへの説明を怠ったり、配当をしていなかったり、あるいは、従業員への還元も不十分で、株価の安い企業は敵対的TOBの標的にされる可能性があることがわかる事件となりました。
このように、TOBやM&Aの実際の例を見てくると、TOBやM&Aとは、株の運用などもやっていない一般の生活者にとっても、決して他人ごとではないことがわかります。
例えば、あなたが勤める会社が、なんらかの理由でTOBを仕掛けられることがあるかもしれません。そうなると、経営方針や業務内容が大幅に変わり、雇用にも影響があるかもしれません。
あるいは、取引先がM&Aされ、その結果、今まで行われてきた取引がなくなってしまうことがあるかもしれません。
TOBやM&Aの報道を他人ごとと思わず、そういった情報にも関心をもつことが大切だと思います。
前回述べた、大手旅行会社による不動産会社へのTOBですが、不動産会社がお願いした対抗TOBは、思わぬ状況となりました。友好的と思われた海外ファンドが不動産会社に対して、雇用その他に手をつけようとしているのです。雇用削減があれば、大きな影響です。
加えて、最近は、投資信託や個人の投資もしやすくなってきています。そういうものを経験してみると、企業を見る目や、経済を見る目が広がってくると思います。
例えば、業績が良くても株主や従業員への還元が不十分な企業は安泰と言えるのか。
あるいは、企業の業績だけでなく、ESGを考慮して投資するとはどういうことなのか。
また、M&Aによる業界再編は企業の事業価値を高めることに繋がりますが、一方で、独占や寡占によってサービスや製品の均一化が進むのではないか。それは、消費者の立場からすると、選択肢が少なくなり、不便になることもあるのです。
実際、銀行の合併によって、近所の支店がなくなったり、いつも行く支店が混み合うようになって不便を感じた経験のある人も多いのではないでしょうか。
企業や経済の動きに関心をもち、さらに、株主のように発言できる立場になることは、自分の生活を守ったり、豊かにすることにも繋がると思います。
従業員の立場からも、敵対的TOBと思っていたら、実は友好的であったり、逆に、友好的に感じたファンドが雇用削減を打ち出したりするので、判断は非常に難しいです。
#1 M&Aってどういうこと?
#2 TOBってどういうこと?
#3 敵対的TOBの成功って、乗っ取り成功のこと?
#4 敵対的TOBが成功しない理由は?
#5 TOBもM&Aも、一般の生活者には他人ごと?
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。