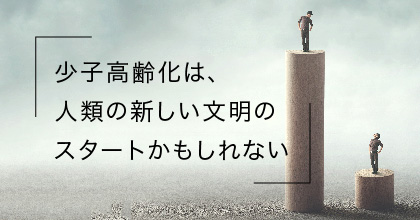少子高齢化は社会に分断を生むかもしれない
前回は、人口減少と少子高齢化について社会の観点から見ましたが、これを個人から見ると、端的に言えば、家系が次々に途絶えていくということになります。
例えば、皆さんの親類を見渡してみてください。世代が下がるほど、兄弟やいとこの数が減っているのではないでしょうか。
いま、孫が1人もいない割合を将来推計も含めて女性の世代別に見ると、80代は9%、50代は31%、20代は41%となります。つまり、いま20代の人の約4割が、孫以降の家系を残さないということになります。
大まかにいうと、この50年の間に、いま日本にある家系の半分くらいはなくなることになるでしょう。
実は、このことは社会保障制度にとっても大問題です。高齢者を支えるベースは、いまでも家族だからです。
高齢者に対する様々な社会保障制度が整えられてきているとはいえ、それは、家族や親族が存在することを前提とするものが大部分です。
この家族・親族ネットワークが構造的になくなっていくとすれば、一人暮らしの高齢者を支えるために社会保障制度をより充実させることが求められます。そのため、社会保障費がさらに膨らむことを懸念する人も多いのではないかと思います。
でも、実は、さらに難しい問題が出てくるでしょう。
まず、子どもを育ててこなかった人たちの老後を、他の人たちが産み育てた子どもたちが支える制度が、その親や子どもたちに受け入れられ続けるのか、という問題があります。
一方で、現在の社会とは、将来の社会に対する投資を常に行っています。すると、子どものいない人たちにとっては、自分たちが払った税金を将来の社会のために使うよりも、現在の自分たちを豊かにするために使って欲しい、と思うようになるかもしれません。
つまり、家族のいない人が増えるということは、社会に分断を生むことに繋がるかもしれません。すると、世代間の支え合いという、いまの社会保障制度の理念が揺らぐだけでなく、社会のあり方に関する人々の考え方に対立が生まれる可能性があります。
こうした状況の要因となっているのが少子高齢化ですが、前回も述べたように、この現象が国レベルで進行することは人類初のことです。しかも、その進行度において、世界の先頭に立っているのが日本なのです。
私たちは、過去や世界の国々のことを検証することはできても、これから日本が直面する社会の手本となる国はどこにもありません。私たち自身が、新しい生き方、新しい社会のあり方を模索しなければならないのです。
次回は、新しい仕組みの考え方について解説します。
#1 少子高齢化による人口減少が問題なのはなぜ?
#2 日本の家系の半分は消滅する?
#3 社会保障制度は、人がつくるもの?
#4 65歳は老後じゃない?
#5 私たちは人類の大転機にいる?
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。