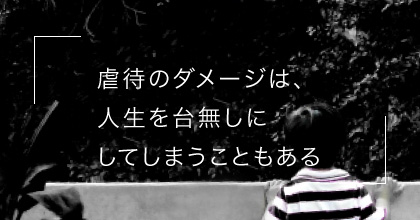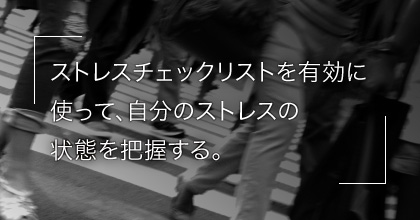
ストレスチェックリストを有効に使って、自分のストレスの状態を把握する。
人は、ストレス状態に置かれ疲れ切っていても、なぜ頑張ってしまうか。その要因のひとつは、自分がストレス状態にあることに気がつかないことです。労働安全衛生法の一部改正により、2015年12月から50人以上の従業員がいる企業は、ストレスチェックを実施することが義務づけられました。ストレスチェックとは、質問項目に自分が当てはまるかどうかをチェックして、ストレッサーやストレス反応の有無、ソーシャルサポート(周囲からの支援)の有無などを客観的に調べるものです。これによって、自分が危険ラインにあるのかがわかり、自分の毎日の生活や、仕事環境などを見直すことができます。つまり、前回説明した適切なストレスコーピングを始めるきっかけになると思います。しかし、会社の定期診断に任せていては年に1回しか行えません。できれば、2~3ヵ月に1回ぐらいのペースで定期的にチェックすることをお勧めします。その際は、精神科や心療内科の病院を訪れるのは大変ですから、そうした病院やストレスケアの機関などがホームページ上に公開しているストレスチェックリストを利用するのが手軽で良いと思います。しかし、その結果、自分が危険ラインを越えていることがわかった場合は、躊躇することなく、病院を訪れていただきたいと思います。病院は敷居が高く感じられるのであれば、心理臨床センターや心の相談機関のようなカウンセリングルームでも構いません。病院だと長い時間話をするのは難しいところもありますが、そうした専門機関であれば、時間をかけてじっくり話を聞いてもらえます。専門家に話を聞いてもらうことが、有効なストレスマネジメントの第一歩といえます。
次回は、専門家はどのように診療するのかについて紹介します。
#1 そもそもストレスってどういうこと?
#2 ストレスを感じない考え方ってある?
#3 最良のストレス対処法は?
#4 自分にストレス症状があるのか気づくには?
#5 相談に行くと専門家は何をしてくれるの?
#6 最良のストレスマネジメント法は?
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。