演劇的生き方のススメ
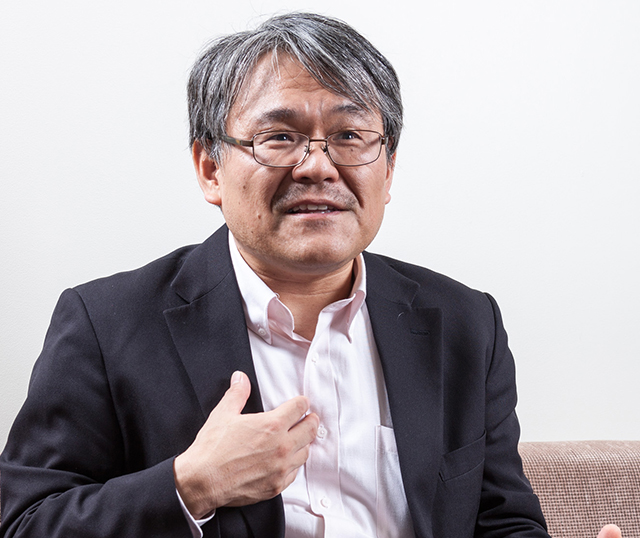 話をシェイクスピアから演劇の方に移しましょう。
話をシェイクスピアから演劇の方に移しましょう。
演劇はどういう芸術でしょうか。
例えば私が今、「パタパタパタ」と自分を扇ぐ動作をしたら、それは「暑いな、室温を下げてほしいな」というメッセージになっているわけです。これは言語ではないので、戯曲の中の台詞にはなりません。しかしこの動作で、冷房を入れて欲しいという気持ちを劇中で俳優が表現し、それを観客が読み取れるというのは、私たちが日常生活で同じ経験をしているからでもあります。
ラブシーンでの「あんたなんか嫌いよ」という一言を、「嫌いって強がっているけど、好きだということの表れだ」と読み取れるのも同じ。つまり、演劇表現と言うのは、言語以外の人間生活の文法がそのまま舞台上に反映されているということにもなります。「嫌い」と文字通りに意味を取ってしまっては、ドラマの鑑賞にもならないし、実生活では恋も始まらないわけですよね。
よく本を読まないと思考が活性化されないなどと言われますが、私は、舞台でもテレビドラマでもいいから、演劇を観ないと人間性が豊かにならないと言いたいですね。
ドラマを見るということは、日常生活のシミュレーションになるわけです。だって、そこで使われているのは、私たちが実際、日常生活で使われているのと同じ文法ですから。だから、私たちは、ドラマを「鑑賞」できますし、逆に考えると、ドラマの中で無意識に体験したことを、日常生活にフィードバックすることもできるのです。
そうしたことも含めて、私たちの日常は、演劇的にできていますし、私たちは日常では常に演技をすることが求められてもいます。「演技をする」というと自分を殺すようなイメージを持つかもしれませんが、自分を伝えるため、自分を生かすために効果的な演技ができたら人生は楽しくなるのも確かです。
だから、いろんなドラマを見て、演劇的感性を身に着けてもらいたいし、「もっと演劇的に生きよう」とも言いたい。
現代は、モノローグ(一人語り)の時代と言われています。さらに近年、SNSが登場したことで、一人語りの傾向が強まっています。SNSは様々な利点もあるのも確かですが、一方で、言いっぱなしのところもある。そこで生まれる関係性も一方的で希薄とも言えるでしょう。一方で、演劇とは、演者同士、演者と観客などダイアローグ(対話)で成立します。そうした演劇的対話は、社会と自分との関係性を相対化し、改めて自分をとらえなおすきっかけも与えてくれる。その意味で、演劇的な対話には無限の可能性があるのです。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。




