「Orpheus」には人の新たな想像力を開花させる可能性がある
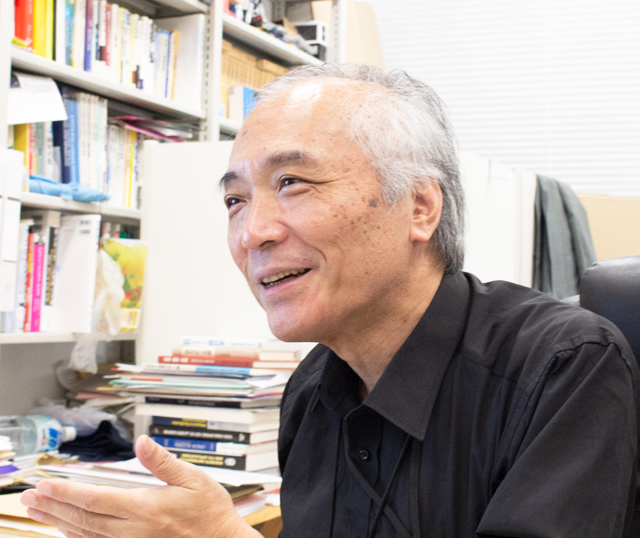 人工知能とはなにかという議論があります。これは意外に曖昧で、例えば、人の機能を機械で実現する研究をしているときは人工知能の研究と呼ばれますが、その技術が実現されると、それを表す新たな技術名がつけられ、人工知能と呼ばれなくなる傾向があります。ともあれ、近年は、深層ニューラルネットや機械学習によるアプローチが最新の手法として注目され、それらを用いた技術を人工知能と呼ぶ傾向にあります。
人工知能とはなにかという議論があります。これは意外に曖昧で、例えば、人の機能を機械で実現する研究をしているときは人工知能の研究と呼ばれますが、その技術が実現されると、それを表す新たな技術名がつけられ、人工知能と呼ばれなくなる傾向があります。ともあれ、近年は、深層ニューラルネットや機械学習によるアプローチが最新の手法として注目され、それらを用いた技術を人工知能と呼ぶ傾向にあります。
私は、確率というアプローチをとっていますが、それは人の思索の機能や、さらには、感覚や感動の仕組みを模擬する有効な方法だと考えています。
例えば、音楽理論は、先人たちの様々な試行錯誤の中で、多数の人にとって快適になる経路を見つけ出し、それを積み上げていったものです。
それを、人は「経験」といいますが、それは、より良い経路にたどり着く確率を見いだす統計学でもあります。すると、人とは、タンパク質でできた統計機械といえるわけです。
であれば、私のアプローチも人の機能の機械実現に近づくものであり、その意味で、「自動作曲」という研究名である「Orpheus」も、人工知能と呼べるものと考えています。
さらに、「Orpheus」によって作られた楽曲は芸術と呼べるか、というと、そうなっていくだろう、と私は考えています。
創作とは、新規性があり、価値があるもののことと考えていますが、「Orpheus」はそうした創作が可能な道具になっていくと考えるからです。
例えば、西洋において、写真技術が登場する以前は、肖像画を描くことは職業でした。しかし、カメラが発達するとともに、肖像画の画家は淘汰されますが、絵画自体は絵画芸術となって残っていきます。
一方、ものを写す道具であるカメラ作品も、写真芸術へと発展していきます。それは、カメラが、筆を動かすという作業から人を解放し、光や時間をどう切り取るかという新規性や価値を生み出す道具となったからです。
いま、「Orpheus」は音楽理論やルールに則り譜面を起こすという手間のかかる作業を軽減する道具になっています。今後、この道具から新規性や価値を生み出すのは、使う人です。
実際、すでに「Orpheus」ユーザーの中には、私も驚くようなスキルを発揮し、優れた作品を作る人が現れ始めています。
近年、人工知能による機械が人の仕事を奪っていくという話が盛んにされ、人工知能を人に敵対するものと捉える人も多いかもしれません。が、人工知能は人を労働から解放して作業の効率を高めたり、また、人の新たな創造力を開花させていく道具ともなると私は考えています。「Orpheus」の発展は、そうした可能性を秘めているのです。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。




