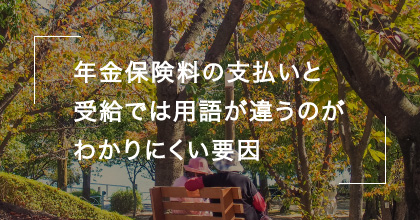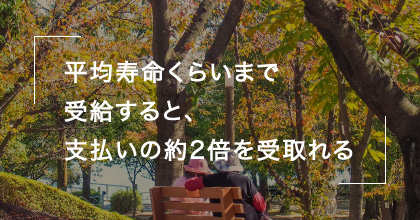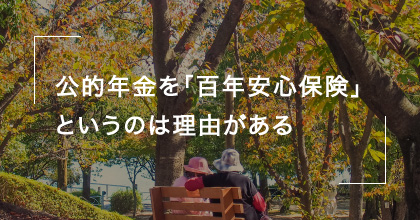学びを加速させるアドバイス実社会がどう動いているかを知れば、学ぶ必要性も見えてくる
教授陣によるリレーコラム/学びを加速させるアドバイス【10】
大学時代は日本思想史を専攻し、卒業後はメーカーで経営管理の職に就きました。しかしほどなく、リーマンショックによる不況に襲われます。注文も入らなくなり、それまで24時間稼働していた工場も動かなくなりました。上司からの指示で私は、コストカットのために非正規雇用の方を主に対象とした人員削減計画を立てることになったのです。
当時は日本の法制度が代わり、製造業にも派遣の仕事が広まっていた時期でした。とはいえ彼らの多くは望んで派遣社員になったわけではなく、たまたま卒業したのが就職の厳しい年であったり、地域的に募集がなかったりといった違いがあるぐらいです。業務に大きな差があるわけでもない。にもかかわらず国が法の仕組みを変え、規制緩和で派遣の業態が広がったがゆえに、不平等を生み出しているのではないかと、大きな疑問を感じました。その経験から、労働者の雇用をより守る社会が望ましいと考えるようになりました。雇用関係を最終的に規律するのは法律です。労働環境を根本的に改善するためには、法学を勉強する必要がある。しかし大学院に行ってしまうと、再び新卒で民間企業に就職するのは難しい。とても悩みましたが、仕事でコストカットの計算をし続けるより、なぜこんなことになっているのか、大もとの法律を勉強しないと自分が納得しないだろうなと思い、退職して学問の道へと進みました。
いつ頃からどのように日本は派遣業が解禁され、派遣可能な業態が広がっていったのか。勉強をするなかで、自分の疑問が解消されていきました。そして今では、労働法の大きな仕組みや、弱者を守る社会権についての研究が、法制度をどう変えるべきかの提案につながる喜びを感じています。
学部生時代は、ただ好きだという理由で日本思想史を学んでいました。しかし法学は、今の社会を少しでも良くしたいと、問題意識をもってから学び始めたものです。法律について学び、手がけた研究が、法改正の役に立つかもしれない。勉強する必要性が明確に見えている分、高いモチベーションで取り組めています。
学生にしろ社会人にしろ、いま取り組んでいる学びの内容に関心が持てないとしたら、「なぜ、その勉強をする必要があるのか」という内的なモチベーションに欠けているのかもしれません。たとえば法律であれば、人権について知ることが自分の身を守ることにもつながります。自分が取り組んでいることの必要性を理解するうえで、まずは社会を見渡し、さまざまな経験をしてみることも大事です。必要性を意識することによって、学びも加速させられるのではないでしょうか。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。