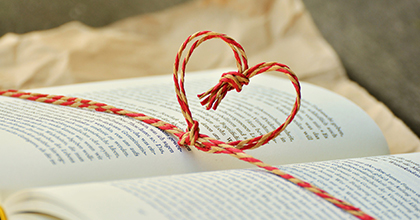語用論の視点から考える翻訳とコミュニケーション
野球の大谷翔平選手に関するニュースでも、日本語と英語のズレを感じる出来事がありました。大谷選手がドジャース移籍後第1号のホームランを打ったときに、そのボールをキャッチした人に対して大谷選手が直接交渉してボールを返却してもらい、見返りの御礼を渡した、と報道されました。しかし、後に、その人は「大谷選手には直接会っていない」と反論し、あたかも大谷選手が真実を曲げて話したかのような印象を与えてしまいました。
これは、大谷選手の「ファンの人と話して、いただけるということだった」という日本語の発言を、通訳者が「I was able to talk to the fan, and I was able to get it back」と訳したことから生じた誤解でした。
日本語では主語がしばしば省略されます。大谷選手は、「球団のスタッフが」という主語を入れずに、主語を曖昧にしたまま話をしたのですが、これは日本語としてはよくあることで不自然ではありません。しかし、英語では主語を明示する必要があり、通訳者が主語の「I」を補って訳してしまったことで、大谷選手本人が直接交渉したかのように受け取られてしまったのです。この問題も日本語と英語のズレに起因していると言えるでしょう。
翻訳の基本は原文を忠実に訳すことですが、そのまま訳すと不自然になってしまう場合も少なくありません。理想的な翻訳とは、読者が翻訳であることを意識せずに読めるものだと私は考えています。しかし、そこで意訳しすぎると、文化的な背景や本来の意味が失われてしまうという問題もあります。
たとえば、日本では店員が丁寧な言葉遣いをするのが一般的ですが、アメリカでは客と対等な関係です。スーパーの店員が飲み物を片手にレジを打つ光景も珍しくありません。日本では、店員が「いらっしゃいませ」と言ってもお客さんは黙っていることが多い一方、アメリカでは「Hello」と言われたら「Hello」と返し、「Have a nice day」と言われたら「Thank you. You too」と返すのが当たり前です。
英語圏の店員とお客さんの会話を日本語に訳すときは、つい店員の口調を丁寧にしすぎてしまいがちです。しかし、実際の英語の会話では、店員もお客さんも対等な口調で話しています。翻訳では、この文化的な違いをどこまで反映させるべきかが悩ましい点です。
近年では、AI翻訳の精度が向上し、ニュースなどでも活用されるようになっています。しかし、語用論の観点から見ると、まだまだ課題が多いと感じます。
たとえば、アメリカのドナルド・トランプ氏の暗殺未遂事件を受けて、カマラ・ハリス副大統領(当時)が「Violence has no place in America」と発言した際、日本のニュースでは「アメリカに暴力は存在しない」と字幕で翻訳されていました。これは実際に、あるAI翻訳を使うと日本語訳される文章です。
しかし、本来の意味は「アメリカに暴力の居場所はない」、つまり「アメリカでは暴力は許されない」というニュアンスが正しいのです。AIは単語の意味を表面的には訳すことはできても、文脈に応じて適切な表現を選ぶことはまだ難しいという例だと思います。
日本語と英語の概念のズレは、私たちが思っている以上にたくさんあります。日本の英語教育ではどうしても文法が中心になりがちですが、実際の異文化のコミュニケーションを円滑にするためには、やはり語用論的な観点を英語教育に導入して語用論的能力を伸ばすことが必要だと私は考えます。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。