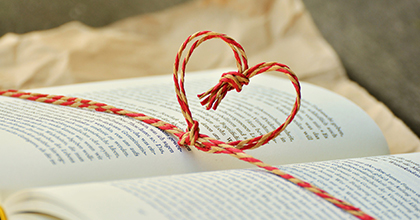「首」と「neck」は同じ? 言語のズレが生む誤解
私のゼミでは翻訳をテーマにしているのですが、翻訳の難しさのひとつは、日本語と英語の「概念のズレ」に起因しています。
英語の単語を覚えるときに、「neck=首」、「cook=料理する」のように、あたかも英語と日本語が一対一でぴったり対応しているかのように覚えた経験が誰にでもあると思います。しかし、一見英語と日本語で同じ意味を持つように見える単語でも、指し示す範囲がズレていることは珍しくありません。
たとえば、日本語の「首」は頭の部分まで含むことがありますが(「首を振る」「首を討ち取る」など)、英語の「neck」に頭の部分は含まれません。また、日本語の「料理する」は火を使わないサラダやサンドイッチにも使えますが、「cook」は火を使う料理に限定されます。
さらに、動詞の切り分けの細かさにも違いがあります。一般的に、英語の方が日本語よりも動詞が細分化していると考えられています。英語では「泣く」(「weep」「cry」「grieve」など)や「笑う」(「smile」「laugh」「grin」など)に多くの動詞があり、それぞれの状況に応じた動詞を使うことが求められますが、日本語では少ない動詞にオノマトペや副詞を付けることでニュアンスを補完しています(「さめざめと泣く」「ニヤニヤ笑う」など)。
もっとも例外はあり、たとえば「wear」に対応する日本語は「着る」「履く」「被る」「身に着ける」など細かく分類されています。このような違いは、その言語が発達した歴史や文化の違いによる可能性があり、一説には、関心の高いものほど単語を細かく分ける傾向があるとも言われています。この説に従えば、日本人は歴史的に体に何かを身に着けるという行為に関心が深かったのかもしれません。
英語から日本語への翻訳の場面でも、こうした概念のズレはさまざまな問題を引き起こします。たとえば、小説『ハリー・ポッター』シリーズの第1巻では、ハリーの母親リリーとペチュニアおばさんの関係について「sister」という単語が使われています。
英語では「sister」で違和感がありませんが、日本語にするときは、姉か妹かはっきりさせないと自然な文になりません。「sister」は最初「妹」と訳されました。しかし、翻訳者である松岡佑子氏が著者のJ.K.ローリングに問い合わせたところ、ハリーのお母さんの方が「姉」であるという回答だったので、第3巻以降はそのように訳すことになったそうです。
ところが、第7巻でペチュニアおばさんが「姉」であることを示す描写があり、また姉と妹がひっくり返ってしまいました。このような混乱は「sister」が「姉」と「妹」の両方を含む、つまり指し示す範囲が違うことから生じた問題です。もしかしたら、英語圏の文化では、きょうだいの年齢が上か下かはさほど重要でないのかもしれません。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。