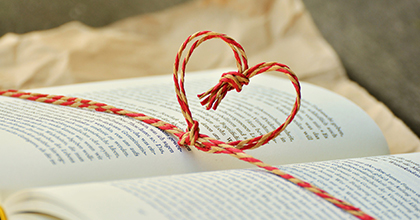英語を話せるようになるために必要なのは、語彙や文法の知識だけではありません。話し手の意図や文化的背景を理解する「語用論的能力」が重要です。本記事では、異文化コミュニケーションにおける語用論的能力の重要性について考察し、さらに、英語と日本語の概念のズレが翻訳にどのような影響を与えるかを、『ハリー・ポッター』や大谷翔平選手の発言を例に解説します。
英語圏に留学すれば英語は本当に上達するのか?
 私は英語教育学や第二言語習得論を専門としており、大学では翻訳のゼミを担当していますが、なかでも言語学の「語用論」と呼ばれる分野を中心に研究しています。語用論とは、簡単に言えば「言葉が実際にどのように使われているのか」を研究する学問です。
私は英語教育学や第二言語習得論を専門としており、大学では翻訳のゼミを担当していますが、なかでも言語学の「語用論」と呼ばれる分野を中心に研究しています。語用論とは、簡単に言えば「言葉が実際にどのように使われているのか」を研究する学問です。
私の研究では、言語の意味が文脈や発話の場面によってどのように変化するのか、また、日本人の留学経験が語用論的能力にどのような影響を与えるのかを調べています。
そもそも、言葉というものは、単に単語の意味や文法を知っているだけでは正しく理解することができません。実際、表面的な意味と話し手の意図が異なっているという現象は、みなさんも日常的に体験しているのではないでしょうか。
たとえば、「明日は雨だよ」という一言でも、文脈によって発話者が意図しているであろうことは変化します。「明日の天気どうかな?」と聞かれて答えた場合には、単なる天候の話になりますが、これが「明日ディズニーランドに行かない?」という誘いに対する返答であったら、暗に「行きたくない」という意図が込められているかもしれません。
こうした場面で「話し手が何を意図して発話しているのか」を正しく理解したり、状況に応じて適切に言語を使用したりする能力が語用論的能力です。外国語の勉強といえば、語彙や文法を思い浮かべる人も多いでしょうが、それだけでは異文化コミュニケーションは必ずしもうまくいきません。
では、留学によって第二言語の語用論的能力はどれだけ伸びるのでしょうか。一般的に、留学すればネイティブスピーカーと触れる機会が増えるため、語用論的能力も自然と向上するのではないかと思われがちです。
しかし、私が半年間の留学経験者の学生を対象に追跡調査を行ったところ、留学前より改善が見られた部分もありましたが、全体的に語用論的能力の伸びは限定的であるという結果が出ました。
その一例が、丁寧表現の能力です。目上の人に何かをお願いをするときに、日本人はしばしば「please+命令形」を使いがちですが、これは実際には命令形ですので、相手に失礼な人だと思わせてしまいます。
私の調査では、留学した学生はこの「please+命令形」こそ使わなくなりましたが、一方で、ネイティブスピーカーなら「I was wondering if〜」や「Would you mind〜」といった丁寧度の高いフレーズを自然に使う場面でも、「Can I~」や「Could you~」というシンプルな表現を一律に使ってしまう傾向がありました。
ただし、測定の方法を変えてみると、新たな発見がありました。半年間留学した学生は、丁寧表現や定型表現を使う能力などはあまり向上しなかったものの、「interactional competence(相互行為能力)」は大きく伸びていたのです。
「interactional competence」とは、実際の会話の中で相手に理解できるように意図を伝え、相手の発言に適切に反応できる能力のことです。留学した学生は、語彙や文法の間違いはあっても、言い換えをしたり、相手の助けを借りたり、ジェスチャーを加えたりして、工夫しながら会話を構築していく力を着実につけていました。やはり、異なる文化圏の人々と日常的に英語でコミュニケーションを取る経験が、相手に自分の意図を伝える力を強化することは間違いないようです。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。