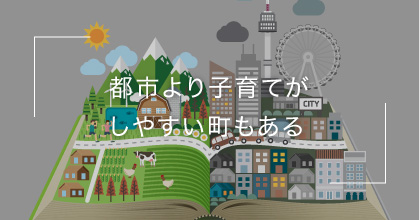
都市より子育てがしやすい町もある
北海道の帯広市の北に上士幌町という町があります。この地域は酪農が盛んで、産業は存在し、職はあるのですが、やはり過疎化と財政難が悩みでした。若者の多くが住みやすい帯広市などに出て行ってしまうのです。
そこで、取り組んだのが「ふるさと納税」の活用です。まず、「ふるさと納税」の仕組みにいち早く取り組み、寄付額でトップクラスの自治体になりました。
しかし、上士幌町の取り組みの要点はその先にあります。町では、集まった寄付を「子育て少子化対策夢基金」として基金化し、その使途を明確化し、子育て世代への支援に重点化しました。
具体的には、認定こども園の完全無償化や賃貸住宅の整備促進などがあります。子育て世代の収入減少を実質的に補填することで、移住者の、年収の減少と子育ての不安を解消することを目指したわけです。
その結果、上士幌町の人口は社会増を達成しました。「ふるさと納税」を財源とした若い世代向けの移住・定住策が成果を上げたのです。
実は、「住みたい町」というのは、地域の創生、活性化にあたってとても重要なポイントです。
北アメリカ西海岸に位置するオレゴン州のポートランドは一地方都市ですが、長年、市開発局(PDC)が都市再生が必要な荒廃した地域を中心に、戦略的なインフラ整備から企業誘致を行い、官民一体となった町づくりを進めてきました。
その結果、今日では、アメリカで最も住みたい町といわれ、その人口は約60万人で、北米西海岸都市の中では3番目に多いのです。町の課題を明確にし、そこを重点的に支援する取り組みは、上士幌町にも共通しています。
「ふるさと納税」のような臨時的な財源が確保されると、多くの自治体では「議会筋」も含めて財政支出拡大要望が強まり、財政規律は緩みがちになります。
しかし、上士幌町は、大切な財源の使途を町の最も重要な課題解決に特化し、選択と集中を行うことに、地域の意見をまとめました。これが成功のポイントなのです。
この「まとまり」が上手くいかず、様々な意見が対立するばかりの地域では、活性化も発展も望めません。こういう状況になると、首長のリーダーシップがとても重要になります。
どうしても調整が上手くいかない場合は、しがらみのない「よそ者」の視点を入れることもひとつの方法になります。実際、首長や自治体の職員を、他地域から誘ったり、公募する事例もあります。
次回は、都市生活者と地方の新たな関係づくりについて解説します。
#1 都市生活者に地方創生は関係あるの?
#2 なぜ、世界では「シリコンバレーモデル」が成功しているの?
#3 地方は、よそ者に排他的なんでしょう?
#4 地方は都市より住みにくいでしょう?
#5 地方創生は都市生活者に何をもたらしてくれる?
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。



