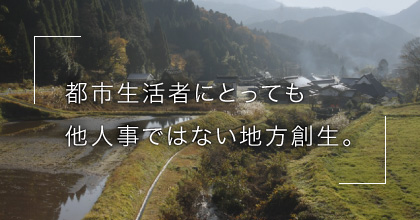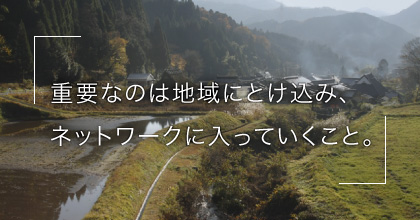人生のターニングポイント恩師から学んだ、危機に備える意識
教授陣によるリレーコラム/人生のターニングポイント【34】
私のターニングポイントは、動物栄養学研究室の前任者である日野常男元教授との出会いです。学問だけでなく、社会に対する心構えなど、たくさんのことを学ばせていただきました。
私が研究室に入った1990年代から、日野先生は地球環境と食糧問題について強い危機感を持ち、警鐘を鳴らされていました。
当時はまだバブル経済に世間の注目が集まっており、“飽食の時代”と言われる中で、食糧危機の話は遠い未来のように思われていました。しかし、今では地球規模の異常気象とともに食糧危機が現実となり、SDGsの達成目標にも挙げられています。
「問題が露呈してから対策を練ってからでは、対応は後手に回ることになり、上手く行かないことが多い。その前から、問題を予見しておき、解決策の方針をいくつか用意しておくことが大事です」
日野先生は常にそのように言われ、解決に貢献する研究に心身ともに注がれてきました。また後進の育成においては、直接的に正解を示すのではなく、自ら解答を導く能力を高める指導をされてきました。
こうした思想や研究は、今になってより重要性が増したと感じられます。そしてビジネスの世界においても、危機管理の意識として非常に役に立つかと思います。
会社や部署を運営して行く中で、順調な時は上を見てしまいがちで、足元には注意が向かないことが多いです。しかし、好調時ほど冷静に問題点を炙り出す必要があるのではないでしょうか。
また、成長曲線をイメージする中でも、起こり得るトラブルを想定し、その解決策についてもいくつか候補を上げていくことが必要と思われます。最悪のシナリオを考えて、見て見ぬふりをしないこと。その上で、選択肢は複数あった方が、問題解決の可能性が高くなります。
今から十年以上前、日野先生は「もしかしたら自分のしてきた研究は無駄になるかもしれません。でも、環境問題や食糧危機が訪れない未来が一番です」とおっしゃっていました。たとえ結果的に使わなかったとしても、その準備自体はとても意義があります。
実際に起こりうるシチュエーションを想定し、最悪の未来にも対応するプランを用意する。それは、科学者にもビジネスパーソンにも通じる大切なことであるように思います。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。