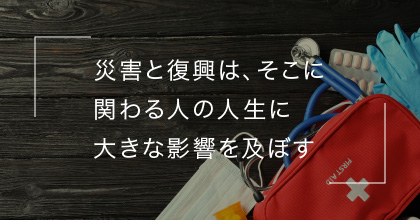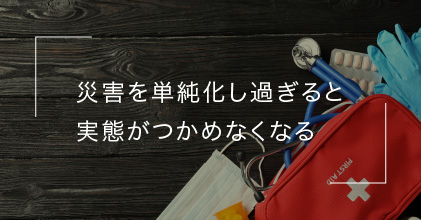
災害を単純化し過ぎると実態がつかめなくなる
近年、日本各地で大きな自然災害が続いています。そのため、最近は、災害に繋がるような自然現象があると注意を喚起したり、避難を促すための情報システムの整備が進められています。また、日頃から災害への備えや準備を促す報道なども数多く見られるようになりました。
もちろん、それはそれで有効なことですが、一方で、わかりやすさを重視し、災害を単純化するような伝え方が増えているようにも思われます。
災害は原因となった自然現象の種別や、被害に見舞われた土地の来歴や構造によって大きく姿を変えますし、遭遇した人、一人ひとりの生い立ちや経験の違いによって、受け取り方も対処の仕方も違ってきます。
つまり、災害とひとくちに言っても、その現場で経験される出来事は千差万別で、一筋縄ではいかないのです。そのため、防災にはこれをすれば大丈夫、という共通の正解は存在しないと言われています。
ひとつ言えることは、まず、より正確な情報や実際の経験に触れることが重要です。
例えば、自治体は地域の「ハザードマップ」を公表していますし、国土交通省は河川の状況をリアルタイムに知ることができる「川の防災情報」をwebサイトで発信しています。
また、東日本大震災などの大きな災害を経験した人が、その体験談を語る活動を行っています。語る人が若者であったり、高齢者であったり、母親や父親であると、それぞれの目線から、なにが起きてどう対処したのかがわかります。
このような実態に即した話を聞くことはとても有意義だと思います。こうした情報に日頃から触れておき、知識をもっておくと、いざというときの初動に役立ちます。
しかし、あらためて言いますが、災害には、前はこうだったから、今度もこうだろう、ということはありません。
実際に災害に遭ったときは、目の前の状況に対する判断を自らせざるを得ない場面があります。そのための選択肢を増やすという意味で、知識を身につけておくことは有効だということです。
この連載では、災害の現場では実際になにが起こるのか、そして、災害から復興するにはどんな困難があり、被災された方々はそれをどうやって乗り越えようとしてきたのか、私たちは日頃からどんな防災意識をもつことが大切なのか。そうした視点から、あらためて災害を見ていきたいと思います。
次回は、災害の現場で実際にどんなことが起こったのかについて解説します。
#1 自然災害の備えに正解はない!?
#2 どうすれば安全な避難ができるの?
#3 住民主体の防災とは自己責任ということ?
#4 復興とは町を元に戻すこと?
#5 災害に備えて私たちにできることは?
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。