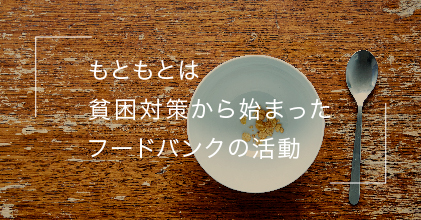
もともとは貧困対策から始まったフードバンクの活動
最近、「フードバンク」という言葉を耳にした人も多いのではないかと思います。
その取り組みは、簡単に言うと、まだ食べられる食品を様々な理由で破棄している企業や生産者、また、食べきれずに余っている食品がある家庭などから、それらの食品を無料で寄付してもらい、食品を必要としている福祉施設や団体、個人などに、原則として無料で提供する活動です。
つまり、まだ食べられるのに破棄される食品を引き取り貯蔵する倉庫であり、それを必要とするところに配布する中継としての機能があるわけです。
このフードバンクが日本で注目されるようになった背景には、コンビニでは消費期限が近づいたお弁当を破棄するといったことが大きく報道されてから、食品ロスについて社会的な関心が高まったことがあると思います。
一方で、福祉の側面もあります。フードバンクの取り組みは、1960年代にアメリカで始まるのですが、そのときは、家庭が貧困で満足に食べられない子どもたちに、社会で余っている食材を届けようという、貧困対策の活動でした。
また、日本では2000年に活動が始まっているのですが、その活動団体のひとつである「セカンドハーベスト・ジャパン」を立ち上げたのは、アメリカ人のチャールズ・マクジルトンさんです。
彼は、日本にも多くのホームレスの人たちがいることを目の当たりにして、アメリカ社会には普通にあるフードバンクの活動を日本でも始めたのです。
つまり、フードバンクの始まりは、食品ロス対策というより、福祉活動の意味が大きかったのです。
一方、日本では2001年に「食品リサイクル法」が施行されます。これは、食品をただ破棄してごみにするのではなく、肥料にしたり、家畜の餌にするなど、有効に活用するための施策です。
その食品リサイクルの中のひとつの方策としてフードバンクが考えられたこともあり、食品ロス対策としてのイメージが強くなったのだと思います。
次回は、フードバンクの具体的な活動について解説します。
#1 フードバンクとは?
#2 フードバンクは食品ロスと生活困窮者を救う?
#3 フードバンクはどれくらいの食品を配布しているの?
#4 フードバンクが正しいというのは間違い?
#5 フードバンクと社会保障制度は連携するの?
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。




