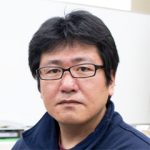スポーツの自動審判も可能になる
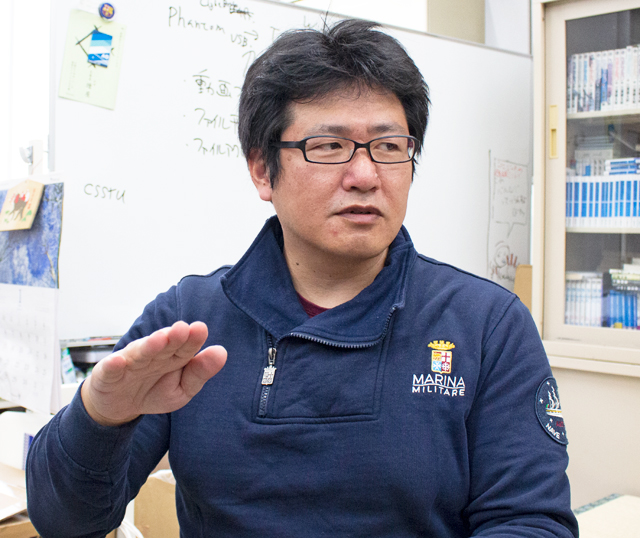 これでは、画像処理技術が向上して素晴らしい技術になっても、社会に導入するのは難しいと思われてしまうかもしれません。
これでは、画像処理技術が向上して素晴らしい技術になっても、社会に導入するのは難しいと思われてしまうかもしれません。
でも、そんなことはなく、実は、様々な分野ですでに実用化も進んでいます。
私たちの身近なところでは、スポーツにおける新たな楽しみ方や、審判の自動化があります。
例えば、野球やテニス、ゴルフなどの様々な球技で、球の軌道を映像化して見せたり、サッカーでは選手の走行距離やプレイエリアなどをデータとして表示するなど、観戦の新たな楽しみを与えてくれるようになっています。そこには画像処理技術が活かされているのです。
また、アメリカのMLBではstatcast(スタットキャスト)というシステムが活用されています。
それは、当初は、選手やボール、バットなどの動きを計測して数値化し、コーチングに活かすシステムでしたが、いまでは、審判の自動化への活用が検討されています。
すなわち、ストライクやボール、セーフやアウトなど、すべての判定をより正確に公平にしようということです。
このシステムが成功すれば、他の様々な競技でも導入が考えられていくのではないかと思います。
実際、すでに多くの競技で、ビデオを活用したジャッジが行われています。それが、審判の自動化に繋がっていくことは充分にあり得ることだと思います。
それは、人でなければ判定できないと思われている採点競技や格闘技、武道などでも可能で、むしろ、それによって公平性が高まることはもちろん、それを受けて選手の競技レベルも向上すると思います。
statcastでは、もともと軍事用だった弾道追尾システムや、高精度のカメラによる画像解析システムなどが応用されています。
しかし、これも自動運転の技術と同じで、誰もが簡単に使える一般的なカメラやパソコンで画像処理をして、解析できるようになれば、プロスポーツが行われるようなスタジアムだけでなく、小さな体育館で行われるような競技会でも、自動審判が実施できるようになると思います。
こうした新しい技術を私たちの生活に取り入れていくためには、私たち自身が技術の発展に関心をもち、メリットやデメリットを正しく知ることもとても重要だと思います。
すなわち、その技術の導入や制度設計をしていくのは、社会に暮らす私たち一人ひとりの意識や知識のレベルだからだと思うのです。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。