線虫から私たちの問題を解決するヒントを得る
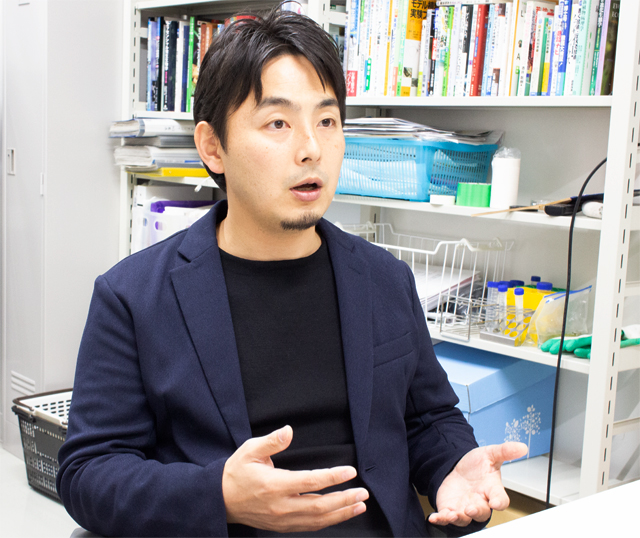 生物のある形質が進化の過程で、もともととは異なる機能や役をもつ形質として転用されることを、前適応と言います。
生物のある形質が進化の過程で、もともととは異なる機能や役をもつ形質として転用されることを、前適応と言います。
モノ湖の線虫は、環境に適応するために前適応的にもともとの形質を転用したと考えられるわけです。
また線虫の一部の種は、他の生物から遺伝子やゲノムのある領域を奪ってきて、子孫にその遺伝子を伝える、遺伝子の水平伝播の機能もあることがわかっています。
さらに、環境条件に応じて生態や形質を変化させる、表現型可塑性と言われる能力も高いため、例えば、完全に乾燥しているような極限環境などでは、餌も食べずに長期間生存する態勢をとることもできるのです。
これらの機能や能力の一つひとつは微生物などにも見られ、線虫独自のものではありませんが、多細胞生物である線虫がそれらを備えていることは、非常に興味深いものがあります。
例えば、ヒ素の代謝を担っている遺伝子など、基本的なところは、人と似ていると考えられるのです。
いま、世界を見渡せば、飲み水に自然界のヒ素が混入し、多くの人が中毒症状で苦しんでいる国があります。
線虫のヒ素耐性のメカニズムが解明できれば、苦しんでいる人たちに無毒化するなにかを摂取させたり、あるいは、その土地に線虫を放すことで、もしかするとヒ素を分解することもできるかもしれません。
私たちが線虫を学び、そこから私たちの問題を解決するヒントを得ることは、これから、たくさんあると思います。
一方で、寄生型の線虫が農作物などに大きな被害を与えていることも事実です。
線虫には上記のような能力があるために、ひとつの殺虫剤に耐性をもつのも早く、殺虫剤の開発との、いわば、いたちごっこが続いています。
私たち研究者は、線虫のもつメカニズムを解明して、人の役に立つ方法と、線虫による被害を防ぐ方法を考える、二本柱で研究を進めています。
皆さんも、線虫には様々な可能性があることをご理解いただき、線虫に関する報道などに対して興味と関心を高めていただければ、それが研究の後押しにもなっていきます。その国のサイエンスの水準を高めるのは、やはり、その国の国民なのです。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。




