すでに私たちの周りで実用化されているロボット技術
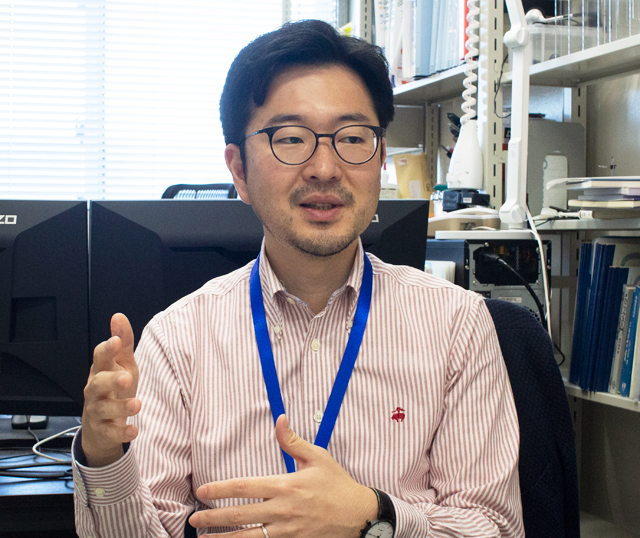 人の能力を超える可能性をもった脚型ヒューマノイドは、災害対応にとどまらず、様々な分野での応用が考えられます。
人の能力を超える可能性をもった脚型ヒューマノイドは、災害対応にとどまらず、様々な分野での応用が考えられます。
例えば、老朽化したインフラやプラントの保守や点検作業です。巨大な建造物の場合、高所での保守点検は危険だし、点検箇所も非常に多いので、人に代わってロボットが作業できれば、うれしいことです。
また、宇宙環境での作業も考えられます。実は、大気圏外の宇宙は放射線が高いため、人が作業することは望ましくないのです。
さらに、月のように低重力の環境だと摩擦が少なく、クローラーなどの車輪型ロボットでは滑ってしまいます。月に降り立った宇宙飛行士がそうであったように、ピョンピョンと跳ねる方が移動速度は速くなります。
そのようなダイナミックな動きができる脚型ロボットの開発も、私たちは進めています。
また、無人宅配ロボットの実用化が目指されていますが、最後の課題となっているのが、まさにラストワンマイル、配達先の玄関まで行くことです。
戸建てでもマンションやアパートでも、玄関にたどり着く前に階段や段差があることが多いのですが、車輪型ロボットでは、どのような段差や階段でも確実に昇れるとは言い切れないのです。
でも、脚型ロボットであれば、人が普通に暮らしている環境の段差や階段であれば、同じように昇り、降りてくることも可能なのです。
このようなロボットの実用化の話は、一般には、まだ先の未来社会のことと思われがちですが、個々のロボット技術自体は、すでに、私たちの周囲で様々な形で応用されています。
例えば、センサで感知し、人が来たことがわかると、ドアを動かして開ける、という自動ドアの仕組みは、ロボット技術を取り入れたものです。これに顔認証システムなどが加われば、さらにロボットらしく思えるのではないでしょうか。
また、人手不足を背景に、コンビニの無人化計画が進んでいますが、商品の陳列や代金の支払い、トイレの清掃まで無人で稼働すれば、それは、コンビニ店舗自体のロボット化です。
実は、東日本大震災のときに最初に投入されたロボットは探査ロボットではなく、ショベルカーやトラックなどの無人の建設機械でした。これによってがれきを撤去し、人や探査ロボットが活動できるようにしたのです。
こうした無人の建設機械は、実は、1991年の雲仙普賢岳の噴火後にも投入されましたし、日常的にも、環境の厳しい作業現場などで稼働しているのです。
一見、ロボットとわからないロボットの方が、私たちの周りで、日常的に実用化されていると言えます。
そして、総合的に人の能力を超える、いわゆるロボットらしいロボットの開発も確実に進んでいます。脚型ヒューマノイドが実用化されたとき、それは、私たちの社会を大きく変えることになるかもしれません。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。




