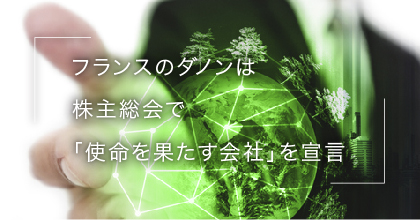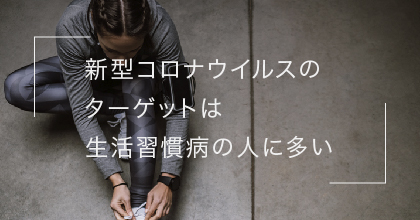
新型コロナウイルスのターゲットは生活習慣病の人に多い
ウイルスは、人の体内に侵入すると、特定のターゲットを攻撃します。例えば、エイズウイルスとして知られるHIVは、白血球のヘルパーT細胞のCD4という分子をターゲットにします。
このヘルパーT細胞は、免疫を担う白血球の中で中心的役割を担っています。要は、免疫の司令官のような存在です。そのため、HIVによってヘルパーT細胞が攻撃されると、免疫機能全体が不全に陥り、エイズを発症することになるのです。
新型コロナウイルスの場合は、ACE2という血圧を調節する酵素をターゲットにします。
簡単に説明すると、血液中には、血圧を高めるように働くアンジオテンシン2というホルモンが分泌されています。生体内で血圧を維持するための昇圧ホルモンです。
しかし、このホルモンが働き過ぎると高血圧になってしまうので、ACE2がこれを分解して、血圧が上がりすぎないように調節するのです。
例えば、肥満になってくると血圧は上がる傾向にあるので、体内ではACE2がたくさん出てきて、血圧を下げようとします。また、糖尿病や高血圧の人の薬には、ACE2の発現を促すような物質が入っています。
つまり、肥満や糖尿病、高血圧など、いわゆる生活習慣病に罹っている人ほど、体内にはACE2が多く出ていることになります。それが新型コロナウイルスのターゲットであったため、そうした病気のある人の体内でこのウイルスの増殖が活発化し、結果として、重症化しやすくなったのです。
生活習慣病を発症すると、健康な生活に戻るのは大変であることは以前から指摘されていますが、今回の新型コロナウイルスでも、生活習慣病は感染しやすく、重症化しやすい要因となったのです。
これは、決して偶然とは言えません。そもそも、健康で適切な免疫力をもった人であれば、ウイルスの感染リスクは低くなるのです。
生活習慣病の人には、健康な人と異なる要素がまだまだあります。それが、未知のウイルスのターゲットになる可能性は、今後もあると思います。
前回述べたように、生活習慣病が文明化社会ならではの病状である以上、こうしたウイルスは、ある意味、人類の高齢化や文明化社会に対する挑戦と言えるかもしれません。
つまり、私たちは、文明の利便性を享受するだけでなく、そこに潜むリスクを認識し、その対策を考え、実行することが重要になるのです。
次回は、適度な運動について解説します。
#1 免疫力を上げればウイルスに負けない?
#2 運動するほど免疫力は上がるの?
#3 ウイルス以外にも見えないリスクってあるの?
#4 生活習慣病の人はコロナに罹りやすい?
#5 健康に暮らすためには工夫が必要?
#6 ライフスタイル・マネジメントってなに?
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。