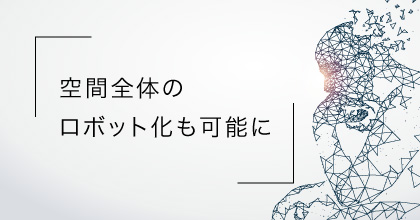
空間全体のロボット化も可能に
ロボットというと、アニメや映画に出てくるような、人型の二足歩行ロボットや動物に似たペットロボットを思い浮かべる人が多いかもしれません。人や動物には、目があり耳があり、手足があり、脳があります。機械やコンピュータにより実現されたロボットも、同じように、感じたり、動いたり、考える部分を持っています。当たり前ですが、人や動物は、目や耳も手足も脳もすべて一体となって形作られています。
では、ロボットはどうでしょうか。人や動物に似せて作ったロボットでは、感じる部分、動く部分、考える部分が一体となってできあがっています。でも、機械やコンピュータは、必ずしも人や動物に似せた形を持つ必要はありません。感じる部分、動く部分、考える部分をどう組み合わせてもいいのです。
例えば、無人コンビニやスマートホームといった賢い空間について耳にする機会が増えてきました。無人コンビニでは、誰が店のどこで何を手にしたかを認識して、購入したかどうかの処理をします。スマートホームでは、人間が部屋のどこにいるかを認識して、照明や空調をコントロールします。どちらも、センサーにより空間で何が起きているかをデータ化し、それを脳にあたるコンピュータに送り、コンピュータがデータを基に様々な指示を出すシステムになっています。これも感じる部分、動く部分、考える部分で構成されています。これもロボットの一つの形です。このように、空間全体としてロボットのように振る舞うものも実現しつつあります。
こちらも話題の自動運転車について考えてみます。自動運転車を単体で見ると、センサーが付いてコンピュータでデータを処理して自動で運転するわけで、まさにロボットです。さらに、それぞれの自動運転車が勝手に走行するだけでなく、交差点の情報、周囲の歩行者の情報、渋滞情報など、広く道路情報を収集し、複数の自動運転車をまとめて制御するというシステムも考えられます。すなわち、都市空間全体がロボットになるという言い方もできるかもしれません。
こうしたシステムが可能になった背景のひとつには、ネットワークの拡充があります。光ファイバーをはじめ、無線もWi-FiやBluetoothなど、様々な通信技術が身近なものになっています。いま話題になっている5Gでは、さらに高速、大容量、多接続、低遅延が実現することになり、様々なシステムの「ロボット化」に拍車がかかるでしょう。
システムの「ロボット化」において、情報収集の入口となるのはセンサーそしてネットワークです。センサーは、人でいえば、目、耳、鼻、口、触覚にあたります。しかし、センサーは人間の五感にとどまりません。近年のセンサーおよびセンサー関連のシステムの発達により、様々な種類のデータを大量に収集可能になっています。このデータを元にして、機械学習やAIなどの情報処理を含めた、生活空間の「ロボット化」が現実的になってきているのです。
次回は、センサーについて解説します。
#1 最新ロボットは人型じゃない?
#2 私たちの身近に広がるセンサー
#3 センサーデータを使ってロボットを賢く!
#4 ロボットは個人の情報を収集している?
#5 センサーデータって誰のもの?
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。



