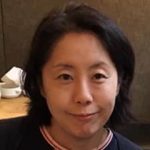近年、SNSなど新しいメディアの影響力が話題になっています。しかし19世紀に社会を動かす影響力を持っていたのは、新聞や小説でした。新聞だけでなく小説にまで世の中を変える力があったというのは意外かもしれませんが、実際、そういう事象はいくつも起こりました。私が研究対象としているヴィクトリア朝時代(1837~1901年)のイギリスを例にご紹介しましょう。
小説に描かれることで、社会問題が広く知れ渡り、政府が動いた時代
 ヴィクトリア朝を代表する作家、チャールズ・ディケンズによる『オリバー・ツイスト』は、1834年制定の「新救貧法」を批判的に描いた小説です。1837年から月刊誌で連載され、1838年に刊行されました。
ヴィクトリア朝を代表する作家、チャールズ・ディケンズによる『オリバー・ツイスト』は、1834年制定の「新救貧法」を批判的に描いた小説です。1837年から月刊誌で連載され、1838年に刊行されました。
当時のイギリスでは、新救貧法では院外救済を禁止とし、働けず貧しくなった人は「救貧院」に入らざるを得ない状況に追い込まれました。しかし救貧院の環境は非常に劣悪です。最低限の食事や意味のない労働を強いられるなど人道的ではなかったため、世界最古の日刊新聞『タイムズ』を中心に反対運動が起こります。
その運動に乗っかるように書かれたのが、『オリバー・ツイスト』です。救貧院で生まれ育つオリバーが、さまざまなつらい目に遭っていく様子を描くことで、タイムズよりもさらにわかりやすい形で、救貧院の酷さを世に知らしめました。これにより反対運動が拡大したことで、当時強大な権力を握っていた救貧法委員が1847年、廃止に追いやられ、救貧院のやり方が改まっていったのです。
次の作品となる1839年刊行の『ニコラス・ニクルビー』では、実際にあったヨークシャーの寄宿学校をモデルにしていました。イギリス北部の僻地であるヨークシャーには、親が厄介払いしたい子供をロンドンなどの大都市から送るような寄宿学校がいくつもあったのです。それにもディケンズは怒りを感じ、自ら取材に行って、極悪非道な校長による非人道的な学校運営を描いています。そのモデルとなった学校は生徒を集められなくなってしまい、閉校に追いやられました。
ディケンズ以外にも、たとえばエリザベス・ギャスケルという女性の作家が1848年に発表した『メアリ・バートン』では、マンチェスターの貧しい人たちの生活が描かれています。マンチェスターの街は、スラム街との境界に中流階級の人たち向けの店舗が並び、富裕層は近くを通っているにもかかわらず、貧民層を一切目にしていませんでした。牧師の妻だったエリザベス・ギャスケルは、貧民に食料を持って行くなどの慈善活動をしており、彼らの生活を知っていたので、作品を通じて現状を伝えることで、社会を変えようとしました。
19世紀は小説が新聞以外の唯一のメディアでした。テレビもない時代ですから、小説に描かれることで広く知られるようになったのです。現代だと小説はあくまでエンタメであり、フィクションであるイメージが強いですが、小説で取り上げることで強い影響力を持つこともできたため、そういった意図をもって書く作家が何人も存在していたのです。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。