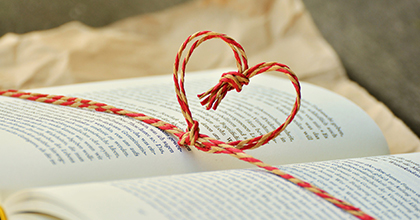アルジェリアには多文化共生のヒントがある
新型コロナウイルスがパンデミックとなったことで、アルベール・カミュの小説『ペスト』が再注目されています。カミュはアルジェリア生まれのフランス人作家で、代表作の『異邦人』も舞台はアルジェリアです。
2014年、この『異邦人』をアルジェリアの人の立場から語り直した『もうひとつの「異邦人」』がフランスで出版され、大きな話題となりました。著者はアルジェリアのジャーナリストとして著名なカメル・ダーウドで、私が日本語訳にたずさわりました。
カミュの『異邦人』を読んだ方はご存じのように、主人公であるフランス人のムルソーは、フランス植民地下のアルジェリアでアラブ人を殺害します。しかし、殺されたアラブ人は誰なのか、『異邦人』の中では名前すら記されていません。
それは、カミュ自身の視線だったのか、植民地のアルジェリアで暮らす当時のフランス人の一般的な視線として、そのように表現されたものなのか、判断は難しいところです。
ダーウドは、この殺されたアラブ人の弟を設定し、その視線で『異邦人』を語り直すわけです。
というと、植民地時代のフランスや、当時のフランス知識人に対する批判が込められているように思われますが、ダーウドにそうした意図はありません。
むしろ、『もうひとつの「異邦人」』には、現在のアルジェリア社会のある種の欺瞞や、イスラーム主義勢力に対する批判が強いのです。
要は、フランスが行った過去にとらわれるのではなく、そのときの自分たち、また、現在の自分たちの存在を描き出すことで、自分たちとアルジェリアのあり方を問うているのです。
それは、ダーウドがジャーナリストだからかもしれませんが、フランスがどうのと言うよりも、常に自分たちの現実に目を向け、そこに対応しようとしてきたアルジェリア知識人らしい姿勢とも言えます。
もちろん、アルジェリアにも反仏を訴える人はいます。一方で、それは社会的、政治的なフィクションでもあると思います。フランスと経済的な関係は強く、文化的な影響や恩恵も大きく受けているアルジェリアは、そのことを自覚しているはずです。
しかし、また一方で、フランコフォニー国際機関(フランス語圏の国を中心とした国際機関)にアルジェリアは加盟していませんし、「フランス語は戦利品」という言葉もアルジェリアにはあるのです。
そこには、フランスの影響を、単に押しつけられたものではなく、自分たちの利益と見なしているようなしたたかさも感じられます。
多様性とか多文化共生を目指すと言いながら、国際社会で英語に頼っている日本は、こうしたアルジェリアに学ぶことは多いのではないかと思います。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。