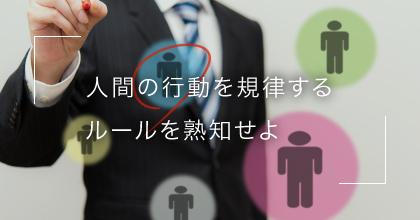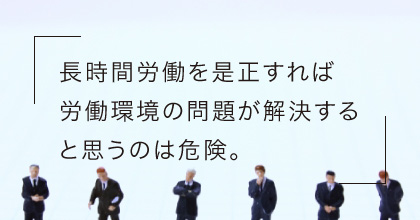人生のターニングポイント「図書館のヌシになりなさい」と言われて
教授陣によるリレーコラム/人生のターニングポイント【62】
これまでの人生でターニングポイントと呼べる場面はいくつかありましたが、最初のそれを挙げるとすれば「高校時代の図書館」でしょうか。
ある日、倫理の授業を担当されていた先生から「図書館のヌシになりなさい」という言葉を贈られました。その時は真意がよくわからなかったのですが、私はアドヴァイスされた通り、それから毎日図書館へ行って閉館まで本を読むようになりました。
その図書館には、なぜだか法律系の書籍がたくさん所蔵されていて、團藤重光先生の『死刑廃止論』など、高校生にとってはハイレベルな本も読むことができました。
通っているうちに、だんだん司書さんとも仲良くなっていきました。実は、その図書館に法学書が多かったのは、司書さんが司法試験の勉強中であったからでした。そんな交流もあって、私はだんだんと法律へ関心を持つようになり、大学は法学部へ入りました。
そこで強く印象に残っているのが、学部1年生の時に受けた著作権法の講義です。初回から国際条約の相互関係についての難しい問題を扱い、別の回では建築家であるフランク・ロイド・ライトの伝記映画を英語で視聴するなど、毎回ちょっと変わった内容で、決して学生から人気の「わかりやすい」授業ではありませんでした。私も3年時と4年時に別の先生の著作権法をあらためて履修し、ようやく法律的な面白さが感じられたほどです。
しかし、高校の時の「図書館のヌシになりなさい」という助言にしても、大学での風変わりな著作権法の講義にしても、最初「よくわからない」と思ったことが、知的財産法の研究という進路へ私を導いたことは確かです。
一見して「よくわかるもの」は、自分にとってさほど大きな意味を持たないのだと思います。すぐに納得して、疑問を持たないまま消えてしまいますから。ひるがえって「よくわからないもの」ほど、スッキリしないがゆえに頭の片隅に居続けるように思います。
「わかりやすさ」が重宝される昨今ですが、本当の学びにつながるのは、疑問や発見の契機となる「よくわからない」経験のほうではないでしょうか。とくに研究者は「わかってしまったらおしまい」です。探求をやめて作業をしているだけになっては意味がありません。
私からビジネスパーソンの皆さんにお伝えできることがあるとしたら、「よくわからないもの」との出会いを大切にしてほしいということ、そして、平等に勉強や議論ができる空間は素晴らしいということです。ぜひ、社会人の方も「よくわからないもの」を持って明治大学へ学びに来ていただきたいと思います。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。