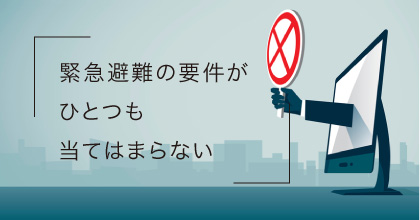アイデアの泉なぜなぜ?と自分の内に問いかけ原因を究明しよう
教授陣によるリレーコラム/アイデアの泉【60】
私は『月刊監査役』という、日本監査役協会が発行している雑誌で2カ月に1回、コーポレートガバナンスに関する事柄について執筆しています。
連載を始めて10年近く経ち、毎回テーマを探すのは大変ですが、読者の方が関心を持つようなテーマを常に探し続け、どのような視点から切り込むべきかを考えています。
そういう意味では、大学の研究者であると同時に複数の会社で社外役員にも就いていることは、研究者と実務者という複眼的な視点を持つことに役立っているのかもしれません。
自分で切り口を見つける際には、なぜか感じるモヤモヤの原因をとことん考え抜くことを大切にしていますが、学生を指導するときによく言うのは「なぜなぜ5回」を実行することです。
「これはどうしてこうなの?」「Aだから。」「Aはなんでそうなの?」「Bだから。」「Bはなんでそうなの?」と、なぜなぜを5回繰り返すと、だいたい本質的なところに落ち着いてくるのです。
研究者に限らず、企業で働く方たちも、例えば「このやり方は効率が悪いけど先輩がずっとやってきたことだから」と流してしまわず、「なぜうまくいかないのか」「どうしたら効率が上がるのか」と考え通すことが必要なのではないでしょうか。
これからの時代は問題解決型ではなく、問題発見型の人材が求められると言います。
問題を発見するためには、自分の外側に課題を求めるのではなく、まず自分の内側を見つめ直すことだと思います。
日常的に見逃してきたことを整理し、熟考した先に、問題へと繋がるヒントがきっとあるはずです。
常に自分のなかに「問い」を持って考え抜くことを心掛けていきましょう。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。