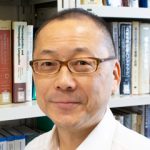プラスチックに限らず廃棄物を減らすリデュースが大切
前回、プラスチックごみ問題の対策として、プラスチック素材を切り替えれば良いわけではないことを説明しましたが、もうひとつ付け加えておきます。
確かに、現在のプラスチックの原料である石油は使い続ければ枯渇してしまうのに対して、紙や植物由来の素材であれば、原料となる植物は再生可能です。しかし、それにも限度があります。
実際、以前は、世界中で森林破壊が大問題と考えられていました。そこで、森林保護と安定した木材資源の確保の観点から、昭和の終わりころからペーパーレス化が推進され、実際、家庭ごみの総量の3割にまで減らすことができたのです。そうしたことを忘れてはいけません。
例えば、日本でもレジ袋の有料化が始まりますが、そのとき、ポリ袋に替えて紙袋にすれば良いだろう、ということではないのです。
根本にあるのは、プラスチックに限らず廃棄物を減らし、資源を大切にするリデュースという考え方です。そのためには、使い続けられる、いわゆるマイバッグを持って行って欲しいのです。
つまりは、プラスチックごみ問題の解決には、政策ももちろん重要ですが、私たち一人ひとりの行動が大切なのです。そのことが忘れられがちになっていると思います。
例えば、ごみ対策の書面などでは、「徹底的に回収する」、「リサイクル率を上げる」、「廃棄物の管理を徹底する」などという言葉が使われ、主語が政府や自治体、企業となっています。
それでは、市民の当事者意識が薄れるのではないでしょうか。直接的に「ポイ捨てや不法投棄をやめてください」と表現した方が伝わると思います。
その意味で、近年、街や駅、観光地などでもゴミ箱が少なくなっているのは問題だと思っています。
テロ防止やごみ回収の費用負担があることはわかりますが、政府や自治体は「徹底的に回収する」ことを目指し、市民に「ポイ捨てや不法投棄をやめてください」と訴えるのであれば、ごみ箱の設置や日々の清掃、ごみ回収について、もっと議論を深るべきだと思います。
プラスチックごみ問題には様々な誤解があることを説明してきましたが、この問題をわかりにくくしている原因の一つに「ごみ」という言葉があると考えています。
使い終わった後に回収されてリサイクル等で再利用されるものは「資源ごみ」、使い終わった後にポイ捨てや不法投棄で自然環境中に排出されてしまったものは「散乱ごみ」と言いますが、日常生活では区別せずに「ごみ」と呼ばれます。もっと良い言い方があれば、区別がわかり易くなるのかもしれません。
でも、確かなのは、「資源ごみ」になるのか、「散乱ごみ」になるのかは、人のモラルによるところが大きいことです。
地道に啓発活動を行う必要があるとともに、私たち一人ひとりがそのことを理解し、行動に繋げていくことが重要であると考えます。
#1 「石油=悪」ゆえに「プラスチック=悪」、は誤解!?
#2 マイクロプラスチックは有害、は誤解!?
#3 日本のプラごみ対策は遅れている、は誤解!?
#4 植物由来プラは自然に還る、は誤解!?
#5 レジ袋は紙袋にすれば良い、は誤解!?
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。