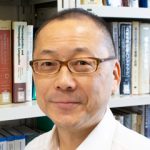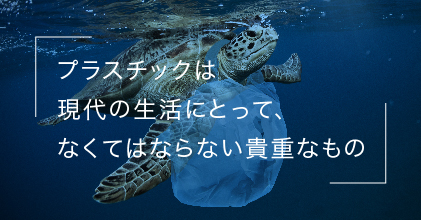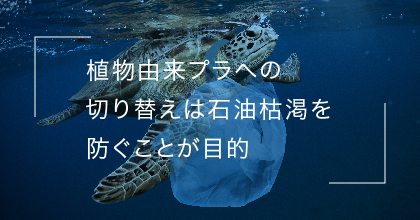
植物由来プラへの切り替えは石油枯渇を防ぐことが目的
海外の飲食チェーン店などでは、使い捨てのプラスチック製ストローを廃止し、紙製やバイオマスプラスチックなどに切り替える動きが出てきています。
これは、確かに意味があることですが、一般に理解されているその意味が少しずれているように思います。
例えば、紙や植物由来のバイオマスプラスチックなどであれば、プラスチックと違い、分解されて自然に還る、というわけではありません。
まず、再生可能な資源である植物に由来する素材に替えることで、石油への依存度を減らすということです。
もうひとつが、紙やバイオマスプラスチックの一部には微生物の作用による生分解性があり、最終的に炭酸ガスと水に分解されるため固体分がなくなることで、ごみの埋立地の寿命を延ばすことに有効であるということです。
つまり、一般に「脱石油」と言うと、石油が悪者だから使わないようにするというイメージで解釈されているようですが、石油は、私たちにとって大切な資源なのです。
それが枯渇していくために、早め早めに代替品を探して依存度を減らしていかなければならない、という意味なのです。
また、植物由来と言うと、環境に優しいというイメージをもたれがちですが、プラスチックを作るために、石油の炭素から化学合成するか、植物の糖を発酵してできたエタノールの炭素から化学合成するかの違いで、最終的には基本的に同じものになります。
ですから、生分解と言っているものも、実は、そう簡単に分解はしません。分解とは微生物によって行われるものですが、その微生物が、自然界のどこにでも都合良くいるわけではないからです。
例えば、研究室での分解実験というと、微生物を含む理想的な条件の下で、半年とか2年間とか置いておき、何パーセント分解されたのかを調べるのです。
つまり、街のアスファルトの上に落ちたストローが、バイオマスプラスチック製であれば分解してなくなる、というようなことではないのです。
実は、ヨーロッパなどではそのことをハッキリと伝えています。植物由来のプラスチックへの切り替えが進むことで、ポイ捨て助長に繋がらないようにするためです。
要は、紙やバイオマスプラスチックの利用は、石油に替わる新しい炭素源の確保と、紙やバイオマスプラスチックの一部の生分解性は、ごみの埋立地の寿命を延ばすために有効ということであり、決して、海などの自然環境中に排出されても安全で問題が無いということはありません。
つまり、プラスチックごみ問題とは、単純に素材を替えれば解決することではありません。やはり、私たち一人ひとりのモラルが問題なのです。
次回は、プラスチックごみ問題について私たちができることについて解説します。
#1 「石油=悪」ゆえに「プラスチック=悪」、は誤解!?
#2 マイクロプラスチックは有害、は誤解!?
#3 日本のプラごみ対策は遅れている、は誤解!?
#4 植物由来プラは自然に還る、は誤解!?
#5 レジ袋は紙袋にすれば良い、は誤解!?
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。