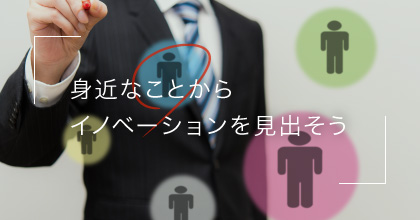40歳までに読んでおきたい本創造力を働かせ、地理学的視点から読み解こう
教授陣によるリレーコラム/40歳までに読んでおきたい本【34】
吉野源三郎『君たちはどう生きるか』(岩波文庫・1982年)
近年、漫画化されてベストセラーとなり、一大ブームを巻き起こした『君たちはどう生きるか』。
昭和初期を舞台に、コペル君という15歳の少年が、叔父さんの助言に導かれながら、日常生活で直面するさまざまな出来事を通じて成長していく物語です。
全体に流れる大きなテーマとして、“倫理的な生き方をしよう”というものはありますが、実は地理的な記述も多く見られます。
たとえば、山の手に住んでいるコペル君が、房州(現在の千葉県南部)に避暑に行くところでは、電車に乗って錦糸町の辺りを通ると工場群が現れ、自分の住む街とは違った風景があり、違った暮らしがあることがわかります。
さらに電車が田園地方に向かうと清々しい風景が広がりますが、その田んぼも避暑に行けない百姓たちが骨を折って作ったものであることに気づくのです。こうしたことが本書のなかにはたくさん含まれています。
また、コペル君が粉ミルクの缶を見て、自分たちの生活が世界と繋がっていることを理解する部分も印象的です。
オーストラリアでつくられた粉ミルクが日本に来るまでには、牛の世話をする人、乳を搾る人、工場に運ぶ人、工場で粉ミルクにする人、缶に詰める人がいて、それが日本に届いた後も、荷物を船から降ろす人、倉庫に運ぶ人、倉庫の番人、小売の薬局など、いろいろな人が携わっています。
このことを経済学で言うと「生産関係」が世界中に広がっているということなのです。資本主義の世の中は物と物との関係にありますが、物の背後には多くの人がいて、私たちの生活を支えてくれています。
そのネットワークがグローバルに広がっているということを、創造力を働かせて読み解いてください。少年の成長物語であると同時に社会科学入門書でもあるのです。
本書は1937年に出版された原作に、政治学者・丸山真男氏による「回想」を加えて文庫化されました。丸山氏の解説はこの視点をより深めてくれるものになっていますので、ぜひ岩波文庫版で読まれることをおすすめします。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。