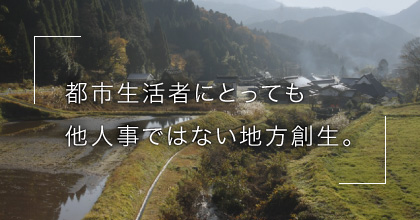40歳までに読んでおきたい本専門分野に別の角度から光をあて発見を引き出そう
教授陣によるリレーコラム/40歳までに読んでおきたい本【32】
中島春紫『日本の伝統 発酵の科学 微生物が生み出す「旨さ」の秘密』(講談社ブルーバックス・2018年)
海堂尊『ジェネラル・ルージュの凱旋』(宝島社・2007年)
『日本の伝統 発酵の科学』は、本学農学部教授の中島氏によって、発酵のおもしろさをサイエンスの面からはもちろん、歴史や文化の面からも考察された一冊です。科学者や理系学生に加え、一般の読者にも幅広く楽しめる内容になっています。
発酵のことがメインに書かれていますが、科学の話だけではなく、サミュエル・ハンチントンの『文明の衝突』といった社会科学の話なども登場し、文系・理系混ざった構成になっているのが魅力です。
それぞれの文明によっていろいろな発酵があることがわかり、社会や歴史などを広く学べ、40代で読むと「ここにきて昔国際関係論で学んだサミュエル・ハンチントンが出てくるんだ、勉強って繋がっていくんだな」と興味深く感じられます。
ただし、チーズや漬物など、発酵食品に関する詳細で愛情あふれる描写は、読んでいると非常にお腹が空いてくるのでご注意ください。
『ジェネラル・ルージュの凱旋』は、映画化やドラマ化もされている人気小説『チーム・バチスタの栄光』シリーズの第3弾となる作品です。
ミステリーとして楽しめる一方、医師でもある海堂氏の作品らしく、単なるエンターテインメントで終わらずに、日本医療の問題点を描いています。
著者は医師として、日本における死亡時の解剖が低いことを問題視し、MRIを検死に利用するオートプシーイメージング(死亡時画像診断)の必要性を訴えていますが、これを小説という形で発表したのが本書です。
社会に新しい技術を導入させたり、みんなをやる気にさせるには通常とは違う方法を取らないと難しいものですが、オートプシーイメージングが大事なんだということを物語にしてしまい、ベストセラーとして世に広めたのは「科学者の新しい形」だと思います。
アカデミックの世界でも、ビジネスの世界でも、新しいことへの挑戦は嫌われがちです。自分の主張を広めるために斬新な手法を使い、うまく社会やムードを変えていく姿勢は敬服に値しますし、皆さんにとっても参考になるのではないでしょうか。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。