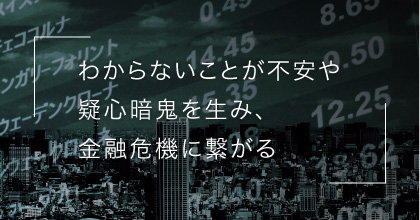たびたび起こる金融危機の共通の要因は、人の心理
株式市場などが大暴落する、いわゆる金融危機は、過去に何度も起こってきました。ひとたび起こると、景気の悪化やそれにともなって失業問題なども招くことがあるので、いわゆる投資家だけでなく、一般の生活者である私たちにとっても日常生活に密接に関わる重大な問題です。1929年、アメリカのウォール街から始まった世界大恐慌は世界中の経済の悪化を招き、それが第2次世界大戦に繋がっていきます。また、1970年代に産油国が石油価格を大幅に上昇させたことから起きたオイルショックでは、日本各地でトイレットペーパーの買い占め騒動が起きたことを覚えている人も多いでしょう。
金融危機は、それを招くなんらかのきっかけが必ずあるので、過去の危機を基にそのきっかけの傾向を捉えれば、危機を予測して未然に防ぐことができるのではないかと思います。しかし、実はそう簡単ではありません。実際、1980年代以降も、ブラックマンデー、日本の土地バブル崩壊、アメリカ同時多発テロ、イラク戦争懸念、リーマン・ショック、ギリシャ危機など、大小様々な金融危機がたびたび起こっています。確かに、それぞれの危機のきっかけとなる事件や出来事は異なります。しかし、共通している要因がひとつあることがわかります。それは、人々の心理です。なにかのきっかけで不安や疑心暗鬼になると、それが瞬く間に伝播、波及し、金融危機に繋がっていくのです。きっかけがわかっているのならばそれを教訓として、常に冷静さや合理的な判断を保つようにすれば良いのではないかと思います。しかし実際は、それが最も難しいことなのです。
次回は、リーマン・ショックを基に、金融危機を防ぐ難しさについて解説します。
#1 金融危機はなぜ起こるの?
#2 リーマン・ショックはなぜ起こったの?
#3 金融危機はなぜ世界に波及するの?
#4 金融危機を防ぐことはできる?
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。