
2015年に「都市農業振興基本法」が成立しました。都市農業が見直されたことはもちろん、農村の土地利用や地域資源の管理など、農業に対する取り組みが変わってきています。その背景には、農業に関わってこなかった都市生活者の意識の変化があります。
都市と農村の「縁」
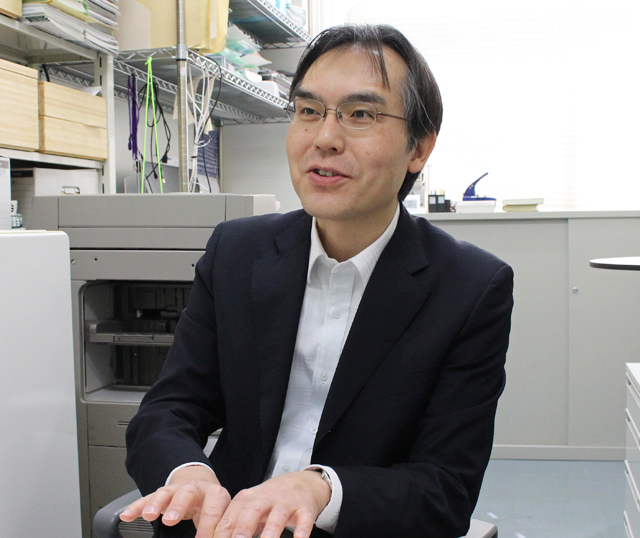 私の関心のある領域を漢字一文字で表すと、「縁(へり)」になります。何事も中心は安定していますが、周辺に向かうほど不安定化します。縁では別のなにかとの衝突が発生し、境となり、解決すべき問題が顕著になるからです。
私の関心のある領域を漢字一文字で表すと、「縁(へり)」になります。何事も中心は安定していますが、周辺に向かうほど不安定化します。縁では別のなにかとの衝突が発生し、境となり、解決すべき問題が顕著になるからです。
農村にも多くの縁が存在します。空間的には、農業と都市のせめぎ合いがある都市近郊の農業。また、農村には農村で、自然との境で鳥獣害が問題となります。海との境である沿岸地域では自然災害が問題となったり、海上では、日本の漁師の利害が他国のそれと衝突することもあります。
また、時間の軸で考えると、高齢の人が多い農家の現役世代と、継承に迷う世代との関係にも境があります。農業に対する取り組みの意識の高さの違いは、同じ農村、同じ世代にもあり、地域内に境を生むこともあります。さらに、成長の時代と現在では、問題の捉え方や、問題そのものが変わっていることもあります。
このように、両側からそれぞれの利害のために押し合いや、せめぎ合いが生じる境が縁なのです。農業や農村における縁に注目することは、日本の農業や農村が抱える問題を考えることであり、日本の農業の持続性を考えることに繋がります。
その意味で、注目したい典型的な縁のひとつが、都市近郊の農業です。1990年代にバブルが弾けるまでの時代は、都市と農村のせめぎ合いは非常に鮮明で、いまよりもリアルでした。
例えば、都市が拡大していく中で、都市近郊の農地は一時利用地のように見なされていました。最終的には、拡大する都市の用地となることがゴールのように思われていたわけです。
また、社会が高度経済成長する中で、農家に生まれた人たちも都市の企業などに就職するようになり、農家は後継者問題を抱えます。また、地価の高騰による相続税の負担など、それでも農業を続けたいという人には厳しい環境になりました。
この状況が変化するのは、バブルが弾けたことにより都市の拡大が止まり、都市農地の変化のゴールがなくなったことです。つまり、都市に飲み込まれることなく、農業を続けていくことができるようになったわけです。だからといって、それで様々な問題が解決したわけではありませんでした。
しかし、都市生活者の農業に対する目線が変わっていったこともあり、農地を取り巻く政策に変化が現れたのです。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。




