縁に目を向けることによって自分の可能性を広げることもある
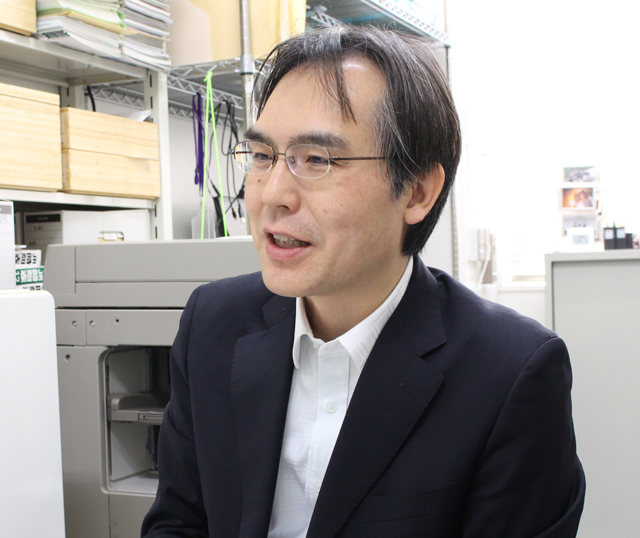 日本の沿岸地域は、海による災害の縁でもあります。2011年の東日本大震災の津波では、それをあらためて思い知らされました。それでも多くの人々が、その地で復興しようとしています。そこには海の恵みがあるからです。
日本の沿岸地域は、海による災害の縁でもあります。2011年の東日本大震災の津波では、それをあらためて思い知らされました。それでも多くの人々が、その地で復興しようとしています。そこには海の恵みがあるからです。
すると、津波の被害を映像などで見た都市生活者がボランティアに行ったり、そこに高さ10mの防波堤を造ることや、高台に住宅地を造成することが推進されます。
日本人はボランティア活動が少ない国民だといわれてきましたが、こうした災害などをきっかけとしてボランティア活動が増えたのは、日本人の心の中にこうした活動を行う気持ちが潜在的にあったからだともいえます。少なくとも、ボランティアに参加した人たちは、沿岸地域の被災を自分たちの問題として捉えたのです。
一方で、海では、その恵みを巡って近隣諸国との衝突が起きています。領海や漁獲高など、決めたルールを守らないことが原因です。しかし、それは映像などで都市生活者に知らされることはほとんどありません。
すると、多くの人は外国との摩擦の方を心配します。問題に直面する漁師たちが我慢して、余計な波風は立てずにいてくれれば良いと思います。国民の総意のようなものが盛り上がらなければ、漁師たちを守るための予算が積極的に投入されることもありません。
確かに、問題に直面する漁師は、圧倒的に少ないかもしれません。しかし、問題は、縁で起きている問題を知ろうとしなかったり、私たちの問題と捉えないことなのです。
縁は地域の問題だけでなく、私たち一人ひとりの生き方にも関わってきます。例えば、会社に勤めている人でも、中心で自分のことしか見ていない人は、縁で起きていることに関心をもちません。
ところが、縁に目を向けると、見える風景が広がり、それは自分の可能性を広げたり、伸ばすことに繋がるかもしれないのです。都市農業に目を向けた都市生活者によって、農業を見る目が変わり、自分自身の生活を豊かにする市民農園が広がっていったように。被災地に目を向けること、知ることによって、ボランティアに駆り立てられたようにです。
まず一度、自分の身の回りから見回してみてください。そこにあった縁にある問題と対峙することが、あなたの行動を広げたり、それがあなたの評価を高めるきっかけになるかもしれないのです。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。




