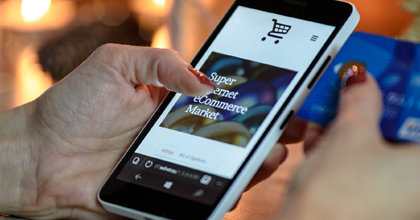科学の発展に馴染まない「選択と集中」
実は、2004年の国立大学の法人化の頃から、科学技術研究予算の配分に関しても、「選択と集中」と言われる考え方が中心的になっています。これは、限られた予算を有望な研究分野に集中的に投下し、より効率的に研究成果を得よう、という考え方です。
そこで、国立大学の運営交付金などを減少させ、代わって、競争的研究資金の割合が増えたのです。つまり、研究者に研究課題などを挙げて申請させ、そこから有望なものを選択して研究費を支給する仕組みです。
しかし、絶対に成功する科学研究が事前にわかることはありません。それは、当たる宝くじだけを買おう、と言っているようなものです。
また、こうした仕組みによって、研究者には、申請書を用意する手間がかかることになりました。実は、こうしたことも問題なのです。
日本の大学の研究力が落ちている要因のひとつは研究資金不足ですが、もうひとつは、研究者の研究に割く時間が減っていることがあるからです。
それは、申請書を作るような事務作業が増えたことや、運営交付金の削減で人件費が削られ、職員の人員が減って、研究者たちが日常的な業務に時間を取られるようになったことなどが原因です。つまり、ここでも悪循環が起きているわけです。
もちろん、限られた予算、それも税金なのですから、有効に使いたいという考え方はわかります。しかし、特に自然科学の場合、その研究が社会に役立つかどうかは、研究者自身にとっても、決して自明ではないのです。
では、研究者はなんのために研究を行っているのか。それは、多くの場合、自然界の仕組みを知りたいという好奇心です。そこで解き明かされたものが、人類の知識として蓄積されてきたのです。
また、研究者の好奇心を科学という形で進めていくには、自由な研究、自由な討論が担保された大学という環境も必要です。
すなわち、「10兆円ファンド」の仕組みも、その背景にある「選択と集中」という考え方も、科学の発展や大学というあり方に馴染まないと言わざるを得ません。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。