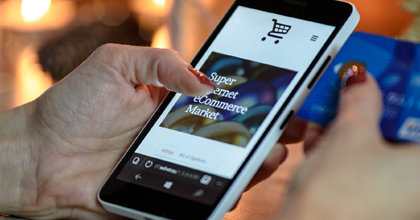近年、日本でも、閉塞した社会状況を打破したり、もうひとつ上のレベルに発展するために、イノベーションに対する期待が高まっています。しかし、イノベーションとはどういった構造から生まれるのか、実は、その研究はあまり成されていないと言うのです。
シュンペーターによって始まったイノベーション研究
 経済成長において、技術進歩やイノベーションが重要であることは、現代では誰もがわかっていることです。
経済成長において、技術進歩やイノベーションが重要であることは、現代では誰もがわかっていることです。
しかし、実は、伝統的な経済成長理論であるソロー・モデルでは技術進歩という要因は外生的要因として扱われているため、「空から降ってくるパン」と揶揄されることもあります。
つまり、経済成長において重要な技術進歩は、突然のプレゼントのように現れるというわけです。
それに対して、アメリカ出身の経済学者であるポール・ローマーが、1986年に内生的経済成長論を唱えます。すなわち、技術進歩はモデルの中で決められ、それができた者が経済成長するということです。
彼はこの理論で2018年にノーベル経済学賞を受賞します。内生的経済成長論の誕生以来、R&D(研究開発)投資は、経済成長の重要な要因として扱われるようになっていきます。
しかし、内生的経済成長論においても、技術進歩やイノベーションがどうやって生み出されるのか、その過程や要因は明確にされていません。
技術進歩やイノベーションが生み出される過程を数式モデルで表すことは容易ではないのです。
すると、技術進歩やイノベーションを生み出すことが重要であると認識し、いくらR&D投資を行っても、いわば、闇雲な投資になりかねないわけです。
こうした伝統的な正統派の経済成長理論に対して、技術進歩やイノベーションのプロセスに迫る研究を行った経済学者がいます。オーストリア出身のヨーゼフ・アイロス・シュンペーター(1883年~1950年)です。
彼は、経済の成長において重要な役割を果たすのは、長期的に見て、技術の進歩であることを強調します。
そして、それは技術の分野だけで成されるのではなく、そこには科学と技術の共進化があると考えられるようになっていきますが、この考えを基に発展させてきたのが、経済学の中では異端派とみなされるネオ・シュンペーテリアンと呼ばれる研究者たちです。
そのひとりであるイタリア出身の経済学者であるジョヴァンニ・ドシは、1982年に「技術パラダイム」という概念を提案しました。それは、特定の科学的原理に基づく問題解決のパターンを意味します。
例えば、ウイルスによる病気が流行すると、人はワクチンを打って備えます。それは、ウイルスによって発症するという問題を解決するために、体内にウイルスの抗体をつくれば防げるという科学的な認識に基づき、抗体の基になるワクチンを打つという問題解決のパターンであるわけです。
つまり、ワクチンは、ひとつの技術パラダイムということです。
しかし、いま、新型コロナウイルスによるパンデミックが起こっています。このウイルスには従来の不活化ワクチンなどでも効き目があるのですが、アメリカやイギリスなどの先進国では、遺伝子組み換えの知識を基に、全く新しいタイプのmRNAワクチンが開発されました。それが、新たな問題解決のパターンになれば、新しい技術パラダイムになっていくわけです。
すなわち、それが従来のパラダイムを変えるイノベーションというわけです。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。