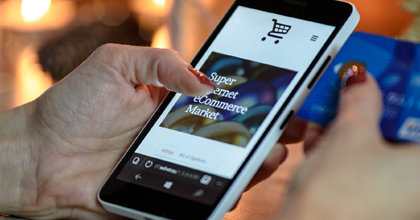重要なのは多様性をもった共鳴場
製薬分野の歴史を基に、技術パラダイムの進歩を述べましたが、このモデルは、様々な産業分野の発展の歴史にも当てはめて考えることができます。
例えば、大気圧の科学的解明が蒸気機関という技術パラダイムを生んでいくこと。元素の科学知識が製鋼の技術パラダイムを生んでいくこともそうです。
人類が道具を使い始めた260万年前から、あらゆる分野において、科学と技術の共進化が技術パラダイムを生み、さらに新しいパラダイムへとイノベーションを起こしてきたと言えます。現代では、それが経済成長へと繋がっていくわけです。
ここで注意すべきは、このイノベーションは、新しい科学的原理に基づく新しい技術パラダイムの出現(「パラダイム破壊型イノベーション」)と、既存の技術パラダイムの中での技術進歩(「パラダイム持続型イノベーション」)とに分けて捉えられることです(京都大学山口栄一教授による分類)。
例えば、先に述べた製薬分野のイノベーションを見ると、ラボアジエの化学革命はまさに新しい科学原理の解明でした。それが基盤となって生まれたワクチンは、それまでの民間療法的なパラダイムを凌駕する、パラダイム破壊型イノベーションであったと言えます。
サルバルサンを改良したネオ・サルバルサンなどの開発は、それまでの科学知識をベースに、技術を少しずつ進歩させたパラダイム持続型イノベーションと言えます。
経済成長という観点から見れば、短・中期的にはパラダイム持続型イノベーションが寄与することも間違いありません。しかし、長期的に見ると、それは逓減し、限界に近づくことは、やはり歴史が証明しています。
そうした状況を打破するのがパラダイム破壊型イノベーションなのです。しかし、そのために必要な革新的な科学知識を得るのは非常に大変な作業です。
例えば、蒸気圧の科学知識を産業技術に応用し、その後の蒸気機関実用化の礎となったフランス出身の物理学者ドニ・パパン(1647年~1712年)は、様々な科学者や技術者と共同研究することで成果を上げていきました。前述の山口教授は、そうした知の分業ネットワークの場を共鳴場と呼んでいます。
新しい科学知識を生み出し、パラダイム破壊型イノベーションに繋がる技術パラダイムを生み出すには、例えば、ひとりの天才に頼るのではなく、様々な科学者や技術者が協力する共鳴場が必要不可欠だと思います。
この共鳴場には、意見や考え方が異なったり、専門の分野も異なる人たちが集うこと、すなわち多様性が重要です。
村社会とか縦割り文化と言われる日本では、わかりあった、いわば同質の者同士が集まり、仲間を組んでひとつの目標に向かうことは得意ですが、その結果、パラダイム持続型イノベーションは起こせても、パラダイム破壊型イノベーションはなかなか生み出せませんでした。
しかし、それでは成長が鈍化し、頭打ちになることは、いま、私たち自身が実感しているのではないでしょうか。
R&D投資を続ければ、いつかブレイクスルーを起こせるというのは、まさに、空から降ってくるパンを待つようなものです。
様々な科学者や技術者による多様性をもった共鳴場、それがオープンイノベーションの本質であり、パラダイム破壊型イノベーションというパンは、そこから生まれるものだと思います。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。