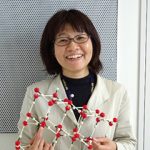新規な材料開発の鍵【ハイドロゲル】
クラスレートハイドレートは、様々な物質を高密度で取り込むことができます。この機能を活かした人工のクラスレートハイドレートの研究も進んでいます。
例えば、過去には、海底のクラスレートハイドレートからメタンを取り出し、代わりに二酸化炭素を入れることで二酸化炭素を海底に貯留するという計画が考えられたこともありました。
また、水素を取り込んだ水素ハイドレートを水素貯蔵材料として活用するという提案もされています。水素ハイドレートは、水素貯蔵合金に比べて軽量であるため、車などに搭載することを考えると、非常に有効であると考えられています。
水が取り込む側となるクラスレートハイドレートに対して、水が取り込まれる側となるハイドロゲルという物質もあります。ハイドロゲルでは、高分子が作る三次元の網目構造の中に水分子が取り込まれるのです。
身近なハイドロゲルの例としては、ゼリーなどがあります。ハイドロゲルは、吸水性と膨潤性が高いため、大量の水を保持することができます。この機能により、ハイドロゲルは紙おむつや除湿剤など、幅広く実用化されています。
私たちは、高分子と共存する水が通常の液体とは異なる物性を示すことに着目し、その構造と性質を解き明かそうとする研究を進めています。高分子材料は、日用品や医用材料の他、様々な場面で活躍する物質であるため、自然界や生体内に大量に存在する水との関わりがとても重要です。
例えば、タイヤに使われるゴムの主成分は高分子です。車が濡れた路面を走っているときは、高分子が水と接した状態となります。タイヤ用ゴムの性能を把握するためには、水と共存した状態での物性を理解することが必要となります。タイヤ用ゴムと接する水の構造や物性が明らかになれば、車の性能をより向上させることができるタイヤの開発に繋がるかもしれません。
一般に水というと、氷、水、水蒸気の三つの状態が思い浮かぶと思います。この三つの状態の変化は、生活の中でも頻繁に目にします。私たちにとって身近な物質であるからこそ、水については既に何もかも分かっていると思えるかもしれません。しかし、視点を変えて水を見てみると、見えていなかった様々な側面があることがわかります。
これは水に限ったことではなく、当たり前と思っていることが、実はそのものの一部の面でしかないこと。そして、新たな一面は、新しい発想や視点を持つことで見えてくることがあります。
こうした発想や視点の転換は、研究者だけでなく、毎日の生活をする上でも大切です。
例えば、上手くいかないと思えることがあったとしても、実は、上手くいっている(もしくは、これから上手くいく)ことに気がついていないだけかもしれない、と。視点を変えてみたら、意外と、違った見え方をすることもあるかもしれません。
※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。